韓国文学翻訳院の仕事の1つは、海外同胞にあまり知られていない韓国語、日本語、その他の言語で書かれた作品をより広い世界の英語文学界に紹介することである。
それには1920年代から1940年代にかけて活躍した韓国の同胞作家らの作品も含まれる。韓国語で話し、韓国語で勉強して読み書きをした彼らの作品は、そのほとんどが日本語で書かれた。韓国作家の初期作の多くは当時の「主要言語」「グローバル言語」だった日本語で書かれ、日本で発刊された。朝鮮後期の人々は、欧州やその他の国の文学作品も日本語版で読んでいた。
韓国文学翻訳院は韓国系の海外同胞が書いた韓国の下層民、つまり日本人でない人々の意見を代弁する過激で政治的な作品も翻訳・紹介している。これらの作品のほとんどは韓国語で出版され、自国語を使って、2等市民に分類されないための政治的な動きを後押しした。これらの動きは韓国・満州・台湾など日本の植民地だった周辺国の全域で現れた。とくに日本の植民地の中でも最も広く野生の地だった満州がその中心となり 吉林省などに住んでいた韓国人の活動が一番目立っていた。
金史良作家の『光の中に』(1939)
金史良(キム・サリャン、1914~1950)作家の『光の中に』は自分のアイデンティティを受け止め、疎外され恵まれない環境に置かれた生徒に父性愛を感じるある教師の物語である。主人公は自分が誰なのか、何なのかについてそれ以上恥を感じることなく、タイトルのように「光の中」と進んでいく。教師は内面の平和を見つける。そして子供も自分のアイデンティティを理解する。物語の最後にはそれほど怒りに満ちていた運転手までもが幸せになる。皆、光の中へと進んでいく。
金史良は作家のペンネームで、本名は金時昌(キム・シチャン)である。彼は東京大学でドイツ文学を勉強し、1943年、29歳のときにソウルに戻る。彼は日本帝国軍で働くことになるが、そこから逃げ出し重慶など中国各地に拠点を置く中華民国国民政府傘下の韓国光復軍のために文章を書き始める。1940年代の初め、北東アジア各地に散在していた多くの韓国人同胞と同様、金作家も1945年8月に韓半島へ戻る。
日本語で書かれ1939年に初めて日本で発刊された彼の短編小説『光の中に』は、つい最近までは韓国で禁書となっていた。親北作家と分類されたからだった。彼の作品は市民個々人を制度で分類する行為と日本帝国に浸透した分類体系について語っている。
南アフリカ共和国のアパルトヘイトについて聞いたことがあるだろうか。それは皮膚に含まれているメラニン色素で人種を区別する政策だった。これと似たようなものが日本による植民地時代にもあった。メラニンではなく、地域と親の出身地から人種を区別するものだった。もし親が本州や九州出身なら、または母国語が日本語なら「日本人」として分類された。そして親が韓国出身か母国語が韓国語の人は「韓国人」とみなされた。親が吉林・黒竜江・遼寧・内モンゴル出身でその地域の言語を使う人は「満州人」に分類された。最も低い4等級に分類されたのは「中国人」だ。この階層分類は南アフリカの人種差別政策と変わらないものだった。
『光の中に』で主人公の教師は「韓国人」と分類された自分のアイデンティティを受け入れる。主人公と生徒、そして運転手は「韓国人であること」を受け止めて内面の平和と満足の中で生きていく方法を学んでいく。
作中の人物らは「韓国人」、当時で言えば「朝鮮人」としてのアイデンティティと「帝国臣民」、つまり「日本人」というアイデンティティの間を彷徨う。身体の特徴では区別がつかない。人物の気構えと登録書類、そして生まれつき持っているものに起因する。使用する言語と目指してきた社会に左右される。
実のところ子供たちは大人より人種差別的な場合がある。
と云った時、戸を開けて覗き込んでいた子供の中、突然大きな声で喚いたものがある。
「そうれ、先生は朝鮮人だぞう!」
山田春雄だった。瞬間廊下はしんとなった。(本文より)
こうして植民地時代を背景にしたこの短編小説には人間が作り出した人種差別主義が蔓延している。そして主人公たちは光の中へ進み、より大きい世界で韓国人として生きていく方法を学ぶ。
同作は植民地時代に非日本人として分類された多くの韓国人が経験せざるを得なかった現実と、当時の時代像を初めて描いた作品の1つである。発表直後に同作は芥川賞の候補作として選ばれ、読者から高い人気を集めた。
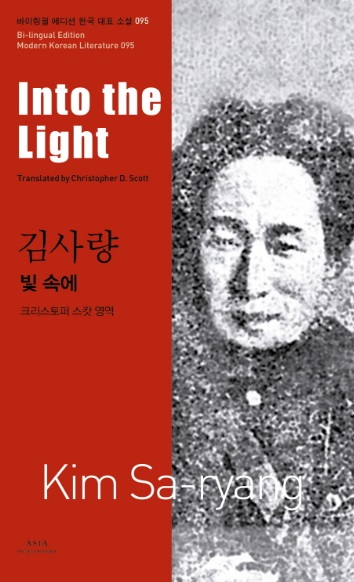
姜敬愛作家の『母子』(1935)
窓が開いてたちまち閉まる。姜敬愛(カン・ギョンエ、1907~1943)作家の短編小説『母子』は戦争と独立運動の暗い面とある女性の運命、そして1930年代を満州で生き抜いた韓国の農民、村の住民たちが直面した現実を語っている。死んでいく女性が死の間際で吐き出す嘆きと生き残るための戦いで、一幕物またはモノローグだとも言える。
「私たちがいくら生き残ろうともがいても結局生き残ることができず死んでしまう」 (本文より)
この作品は明るい内容ではないが、1930年代の韓半島北部と南満州に住んでいた韓国人、なかでも韓国女性の人生にフォーカスを当てている。
『母子』は戦いに関する物語で、苦痛の話でもある。姜敬愛作家は主にフェミニズム闘争と労働階級、下層民の戦いを描いた作品を書いた。『母子』は韓国の民族主義運動家、または独立運動の苦しみと戦いを描いた。1910年からの植民地主義により、韓国は1930年代まで苦痛を強いられた。
同作はひとりの女性の苦しみと母親として子供を助けようとするその戦いの物語である。ひとり親の母としてのアイデンティティと社会的立場にフォーカスを当てている。解体された家族、大家族の苦痛についても語る。背景のストーリーから天気、短い会話に至るまで「スンホの母」としか呼ばれない主人公は、苦しんで、苦しんで、苦しみ続け、呪われた人生の逆境と苦難を耐え抜く。冷たく憂うつなストーリーだ。
姜敬愛作家は中国の延辺に住んでいた。延辺は現在と同様、1930年代にも吉林省内の韓国人社会の中心だった。韓半島の北側、中でも吉林省の冬は過酷で身を切るような風がシベリア平原から吹きすさび、数カ月にかけて乾いた雪と零下の寒さに襲われる。貧しくて家のない人々、嵐の中にも身を任せるところがなく子供の世話をしなければならない人たち。これらすべてが姜敬愛作家の作品に登場する。
苦痛を強いられる女性の人生が11ページの短い短編に溶け込んでいる。スンホの母は嵐から逃れる場所を見つけるために村のあちこちを走り回る間にも、ずっと幼いスンホを負んぶしている。夫が死んでしまい独り身になった彼女は、自分が属している社会でも居場所を見つけることができずさら苦しむ。
最後に作家は下層民の苦しみについて語る。『母子』のような短編作品には共産主義革命やフェミニズム革命を促す力がある。短編作品により人々は街に出てより良い世界に向けて前進する力を得られる。
この作品は1935年、ある新聞に韓国語で掲載され韓国の読者たちに遠い満州の田舎でひとりの女性が経験した苦難を伝えた。韓国人が耐えなければならなかった貧困の物語は、日本の植民地として抑圧されていた韓国人によく伝わった。姜敬愛作家は現代の女性がそうであるように、当時の女性たちが直面した現実にフォーカスを当てた。私たちにはなかなか見えない、おそらく見ることのできない世界のストーリーを生々しく文章で表現したのだ。
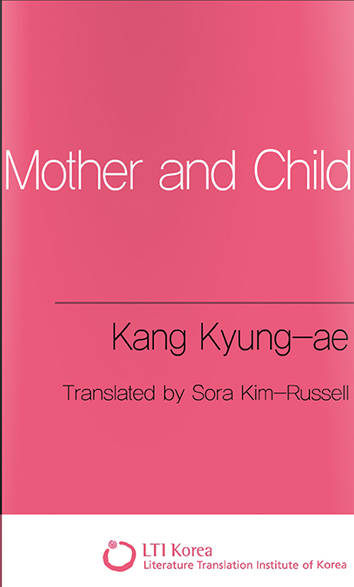
韓国文学が本格的に花を咲かせた時期は1910年代の後半だった。1917年に毎日新報で連載された李光洙(イ・グァンス)の『無情』からもそれがわかる。この作品は韓国人が書いた初めての現代小説だとされる。同作で李光洙は言語と民族主義、浪漫主義で実験的な試みをしてみせた。しかし、同胞文学がしっかり花を咲かせ始めたのは1930年代に入ってからで、そのうちわずか半分だけが韓国語で書かれた。

1919年以降、植民統治下の韓国に対する日本の政策に変化が現れた。1919年3月1日に泰和館(テファグァン)に集まった33人の独立運動家に触発された「独立万歳運動」により、日本は韓国人が日本の抑圧を大人しく受け入れないであろうことを認識したのだ。
1920年代になって日本の規制が緩くなったことで韓国語で芸術・文学作品を作ることがより容易になった。しかし、1920年代の朝鮮文学は国家としてのアイデンティティを守るための道具に近く、独立と密接に結びついていた。人々の日常を描いた金東仁(キム・ドンイン、1900~1951)の『親指が似ている』(1932)と玄鎭健(ヒョン・ジンゴン、1900~1943)の『貧妻』(1921)のような作品も発表されたが、1920年代の文学傾向は1925年に創設された「朝鮮プロレタリア芸術家同盟(KAPF)」が主導する共産主義とプロレタリア文学だった。
独立運動を実現するためだというその意図は理解できるとしても、文学を民族主義と共産主義の道具として活用する流れに反発する新たな動きが文学界に現れた。それをリードしたのは文学グループの「九人会」だった。李箱(イ・サン、1910~1937)、朴泰遠(パク・テウォン、1909~1986)などで代表される九人会は文学を単なる道具として利用する傾向を拒否し、文学そのものを尊重することを主張した初めての文学グループだった。
九人会の作家らは著者の性格と創作の方式を尊重し、より多様なテーマを扱う新しい創作の方式が1930年代に入って現れ始めた。超現実主義作家の李箱は、都市化したソウルを小説と詩で表現した。日本で勉強し西欧文学からインスピレーションを得て影響を受けた作家の朴泰遠は、小説『小説家の仇甫氏の一日』で「意識の流れ」という手法を取り入れた。九人会という文学グループ自体は数年しか維持できず、そのメンバーも入れ替わりが多かったが、韓国文学界では最も重要な文学グループだとされる。 1930年代からはより多くの小説が発表された。廉想涉(ヨム・サンソブ、1897~1963)の『三代』や蔡萬植(チェ・マンシク、1902~1950)の『濁流』のような小説作品もこの時期に登場した。
コリアネット グレゴリー・イーヴス記者
写真:韓国文学翻訳院
翻訳:コリアネット ソン・ジエ記者、イム・ユジン
gceaves@korea.kr
それには1920年代から1940年代にかけて活躍した韓国の同胞作家らの作品も含まれる。韓国語で話し、韓国語で勉強して読み書きをした彼らの作品は、そのほとんどが日本語で書かれた。韓国作家の初期作の多くは当時の「主要言語」「グローバル言語」だった日本語で書かれ、日本で発刊された。朝鮮後期の人々は、欧州やその他の国の文学作品も日本語版で読んでいた。
韓国文学翻訳院は韓国系の海外同胞が書いた韓国の下層民、つまり日本人でない人々の意見を代弁する過激で政治的な作品も翻訳・紹介している。これらの作品のほとんどは韓国語で出版され、自国語を使って、2等市民に分類されないための政治的な動きを後押しした。これらの動きは韓国・満州・台湾など日本の植民地だった周辺国の全域で現れた。とくに日本の植民地の中でも最も広く野生の地だった満州がその中心となり 吉林省などに住んでいた韓国人の活動が一番目立っていた。
金史良作家の『光の中に』(1939)
金史良(キム・サリャン、1914~1950)作家の『光の中に』は自分のアイデンティティを受け止め、疎外され恵まれない環境に置かれた生徒に父性愛を感じるある教師の物語である。主人公は自分が誰なのか、何なのかについてそれ以上恥を感じることなく、タイトルのように「光の中」と進んでいく。教師は内面の平和を見つける。そして子供も自分のアイデンティティを理解する。物語の最後にはそれほど怒りに満ちていた運転手までもが幸せになる。皆、光の中へと進んでいく。
金史良は作家のペンネームで、本名は金時昌(キム・シチャン)である。彼は東京大学でドイツ文学を勉強し、1943年、29歳のときにソウルに戻る。彼は日本帝国軍で働くことになるが、そこから逃げ出し重慶など中国各地に拠点を置く中華民国国民政府傘下の韓国光復軍のために文章を書き始める。1940年代の初め、北東アジア各地に散在していた多くの韓国人同胞と同様、金作家も1945年8月に韓半島へ戻る。
日本語で書かれ1939年に初めて日本で発刊された彼の短編小説『光の中に』は、つい最近までは韓国で禁書となっていた。親北作家と分類されたからだった。彼の作品は市民個々人を制度で分類する行為と日本帝国に浸透した分類体系について語っている。
南アフリカ共和国のアパルトヘイトについて聞いたことがあるだろうか。それは皮膚に含まれているメラニン色素で人種を区別する政策だった。これと似たようなものが日本による植民地時代にもあった。メラニンではなく、地域と親の出身地から人種を区別するものだった。もし親が本州や九州出身なら、または母国語が日本語なら「日本人」として分類された。そして親が韓国出身か母国語が韓国語の人は「韓国人」とみなされた。親が吉林・黒竜江・遼寧・内モンゴル出身でその地域の言語を使う人は「満州人」に分類された。最も低い4等級に分類されたのは「中国人」だ。この階層分類は南アフリカの人種差別政策と変わらないものだった。
『光の中に』で主人公の教師は「韓国人」と分類された自分のアイデンティティを受け入れる。主人公と生徒、そして運転手は「韓国人であること」を受け止めて内面の平和と満足の中で生きていく方法を学んでいく。
作中の人物らは「韓国人」、当時で言えば「朝鮮人」としてのアイデンティティと「帝国臣民」、つまり「日本人」というアイデンティティの間を彷徨う。身体の特徴では区別がつかない。人物の気構えと登録書類、そして生まれつき持っているものに起因する。使用する言語と目指してきた社会に左右される。
実のところ子供たちは大人より人種差別的な場合がある。
と云った時、戸を開けて覗き込んでいた子供の中、突然大きな声で喚いたものがある。
「そうれ、先生は朝鮮人だぞう!」
山田春雄だった。瞬間廊下はしんとなった。(本文より)
こうして植民地時代を背景にしたこの短編小説には人間が作り出した人種差別主義が蔓延している。そして主人公たちは光の中へ進み、より大きい世界で韓国人として生きていく方法を学ぶ。
同作は植民地時代に非日本人として分類された多くの韓国人が経験せざるを得なかった現実と、当時の時代像を初めて描いた作品の1つである。発表直後に同作は芥川賞の候補作として選ばれ、読者から高い人気を集めた。
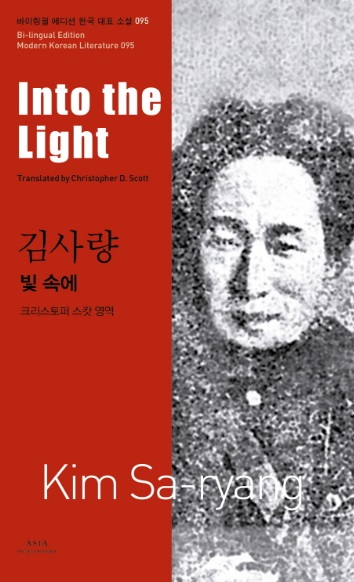
金史良作家が1939年に日本語で書いた短編小説『光の中に』は、後日韓国語に翻訳・出版された
姜敬愛作家の『母子』(1935)
窓が開いてたちまち閉まる。姜敬愛(カン・ギョンエ、1907~1943)作家の短編小説『母子』は戦争と独立運動の暗い面とある女性の運命、そして1930年代を満州で生き抜いた韓国の農民、村の住民たちが直面した現実を語っている。死んでいく女性が死の間際で吐き出す嘆きと生き残るための戦いで、一幕物またはモノローグだとも言える。
「私たちがいくら生き残ろうともがいても結局生き残ることができず死んでしまう」 (本文より)
この作品は明るい内容ではないが、1930年代の韓半島北部と南満州に住んでいた韓国人、なかでも韓国女性の人生にフォーカスを当てている。
『母子』は戦いに関する物語で、苦痛の話でもある。姜敬愛作家は主にフェミニズム闘争と労働階級、下層民の戦いを描いた作品を書いた。『母子』は韓国の民族主義運動家、または独立運動の苦しみと戦いを描いた。1910年からの植民地主義により、韓国は1930年代まで苦痛を強いられた。
同作はひとりの女性の苦しみと母親として子供を助けようとするその戦いの物語である。ひとり親の母としてのアイデンティティと社会的立場にフォーカスを当てている。解体された家族、大家族の苦痛についても語る。背景のストーリーから天気、短い会話に至るまで「スンホの母」としか呼ばれない主人公は、苦しんで、苦しんで、苦しみ続け、呪われた人生の逆境と苦難を耐え抜く。冷たく憂うつなストーリーだ。
姜敬愛作家は中国の延辺に住んでいた。延辺は現在と同様、1930年代にも吉林省内の韓国人社会の中心だった。韓半島の北側、中でも吉林省の冬は過酷で身を切るような風がシベリア平原から吹きすさび、数カ月にかけて乾いた雪と零下の寒さに襲われる。貧しくて家のない人々、嵐の中にも身を任せるところがなく子供の世話をしなければならない人たち。これらすべてが姜敬愛作家の作品に登場する。
苦痛を強いられる女性の人生が11ページの短い短編に溶け込んでいる。スンホの母は嵐から逃れる場所を見つけるために村のあちこちを走り回る間にも、ずっと幼いスンホを負んぶしている。夫が死んでしまい独り身になった彼女は、自分が属している社会でも居場所を見つけることができずさら苦しむ。
最後に作家は下層民の苦しみについて語る。『母子』のような短編作品には共産主義革命やフェミニズム革命を促す力がある。短編作品により人々は街に出てより良い世界に向けて前進する力を得られる。
この作品は1935年、ある新聞に韓国語で掲載され韓国の読者たちに遠い満州の田舎でひとりの女性が経験した苦難を伝えた。韓国人が耐えなければならなかった貧困の物語は、日本の植民地として抑圧されていた韓国人によく伝わった。姜敬愛作家は現代の女性がそうであるように、当時の女性たちが直面した現実にフォーカスを当てた。私たちにはなかなか見えない、おそらく見ることのできない世界のストーリーを生々しく文章で表現したのだ。
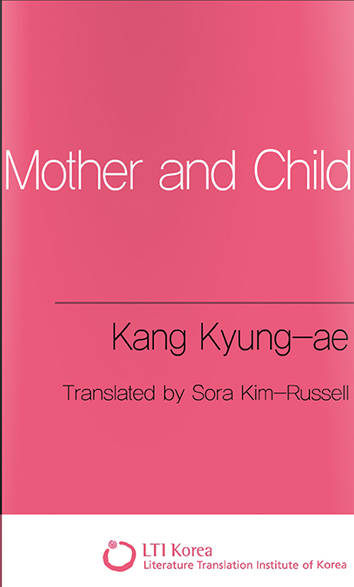
姜敬愛作家は1935年に韓国語の短編小説『母子』を発表した。当時、作家は過激なフェミニスト、社会運動家として みなされた
韓国文学が本格的に花を咲かせた時期は1910年代の後半だった。1917年に毎日新報で連載された李光洙(イ・グァンス)の『無情』からもそれがわかる。この作品は韓国人が書いた初めての現代小説だとされる。同作で李光洙は言語と民族主義、浪漫主義で実験的な試みをしてみせた。しかし、同胞文学がしっかり花を咲かせ始めたのは1930年代に入ってからで、そのうちわずか半分だけが韓国語で書かれた。

姜敬愛作家は主にフェミニズム闘争と労働階級および下層民の戦いなど社会問題に注目した作品を書いた
1919年以降、植民統治下の韓国に対する日本の政策に変化が現れた。1919年3月1日に泰和館(テファグァン)に集まった33人の独立運動家に触発された「独立万歳運動」により、日本は韓国人が日本の抑圧を大人しく受け入れないであろうことを認識したのだ。
1920年代になって日本の規制が緩くなったことで韓国語で芸術・文学作品を作ることがより容易になった。しかし、1920年代の朝鮮文学は国家としてのアイデンティティを守るための道具に近く、独立と密接に結びついていた。人々の日常を描いた金東仁(キム・ドンイン、1900~1951)の『親指が似ている』(1932)と玄鎭健(ヒョン・ジンゴン、1900~1943)の『貧妻』(1921)のような作品も発表されたが、1920年代の文学傾向は1925年に創設された「朝鮮プロレタリア芸術家同盟(KAPF)」が主導する共産主義とプロレタリア文学だった。
独立運動を実現するためだというその意図は理解できるとしても、文学を民族主義と共産主義の道具として活用する流れに反発する新たな動きが文学界に現れた。それをリードしたのは文学グループの「九人会」だった。李箱(イ・サン、1910~1937)、朴泰遠(パク・テウォン、1909~1986)などで代表される九人会は文学を単なる道具として利用する傾向を拒否し、文学そのものを尊重することを主張した初めての文学グループだった。
九人会の作家らは著者の性格と創作の方式を尊重し、より多様なテーマを扱う新しい創作の方式が1930年代に入って現れ始めた。超現実主義作家の李箱は、都市化したソウルを小説と詩で表現した。日本で勉強し西欧文学からインスピレーションを得て影響を受けた作家の朴泰遠は、小説『小説家の仇甫氏の一日』で「意識の流れ」という手法を取り入れた。九人会という文学グループ自体は数年しか維持できず、そのメンバーも入れ替わりが多かったが、韓国文学界では最も重要な文学グループだとされる。 1930年代からはより多くの小説が発表された。廉想涉(ヨム・サンソブ、1897~1963)の『三代』や蔡萬植(チェ・マンシク、1902~1950)の『濁流』のような小説作品もこの時期に登場した。
コリアネット グレゴリー・イーヴス記者
写真:韓国文学翻訳院
翻訳:コリアネット ソン・ジエ記者、イム・ユジン
gceaves@korea.kr