古宮、韓服、キムチ、Kポップ…。「韓国」といえば外国人がよくイメージするものだ。だが、もっと幅広い観点から韓国を紹介する本がこのほど出版された。
韓国在住20年目でホンイク(弘益)大学教授のベンジャミン・ジュアノ(Benjamin Joinau)さんが執筆し、エロディ・ドルナン・ド・ルーヴィル(Elodie Dornand de Rouville)さんがイラストを担当した『スケッチーズ・オブ・コリア(Sketches of Korea)』だ。
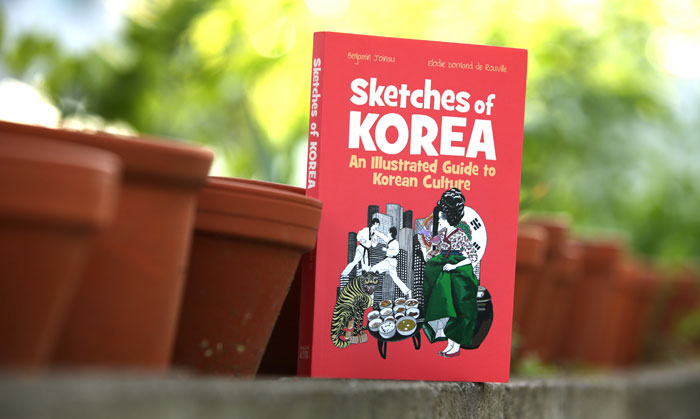

同書は、韓国の飲酒文化や爆弾酒(アルコール度数の高いウィスキーや焼酎をビールに混ぜたもの)、慶弔事の祝儀金と香典、銭湯で知らない人同士で背中を流し合うことなど、外国人がほとんど目にしない風景に注目している。また、「フンナム」(温かい雰囲気の男性)や「コンミナム」(イケメン)といった言葉を紹介しながら韓国社会の外見至上主義について説明する。
著者のジュアノさんは、現代だけでなく、伝統と芸術、韓国フードについても、イラストを交えながら事実に基づいて説明している。特に、キムチのレシピと歴史について紹介し、「フランスではバゲット、イタリアではパスタのように、キムチは韓国民族の遺産(national heritage)で万能薬(panacea)のようなもの」と論じる。伝統芸術では、山水画や風俗画、古家具など、韓国人もあまり知らないことについても紹介している。
ジュアノさんの目に映る韓国の社会と文化、そして韓国とフランスに対する思いについてインタビューした。

‐『スケッチ・オブ・コリア』を執筆しようと思った動機は。
韓国で暮らし始めて約20年になるが、当時は外国語で書かれた韓国に関する本、特にフランス語で書かれた本はほとんどなかった。それで、韓国に来る準備にとても苦労した。実際に韓国に来て道に迷うことが多く、それ以上にカルチャーショックが大きかった。もちろん、謎解きのような楽しさもあった。しかし、私のように韓国を体験した一部の人を除き、暇のないほとんどの人には資料があまりにも少なすぎると思った。
1998年にフランスの某出版社とともに韓国の旅行ガイドブックを出版した。私が初めて執筆した韓国に関する本だ。その本もある程度有用だとは思ったが、単なる道案内だけでなく、目的地にたどり着くために必要な文化的知識を紹介することが必要だと思った。その本を執筆する6~7年前にも書店に行けば英語で書かれた韓国紹介書はあったが、それでは不十分だと思った。 いくら本のデザインがきれいでも、ほとんどが韓国人の目から見た本だったからだ。内容のほとんどが外国人の見方と一致しないものが多く、外国人を対象にしてはいるものの韓国人が一番良いと思うものを紹介しているものばかりだった。例えば、メドゥプ(朝鮮半島に伝わる飾り結び)やポデギ(おんぶ紐)などは、韓国らしいものだが、歴史的・文化的な深みがないと思った。そうした本は、見かけはきれいでも、あまり役に立たない「コーヒーテーブル・ブック」に過ぎない。だから、本の構想についてエロディさんと話し合い、多くの人は本を読むとき、文字よりも先に絵を見るので、イラストを入れたほうが効果的だという意見で一致した。人は誰でも視覚的なもののほうに先に目がいくのだから。それで私たちは、「イラストで見る韓国の本」を制作することにした。
次に、朝鮮時代末期の韓国ではなく、私たちが日常的に目にする現在の韓国の姿を見せ、説明する必要があると思った。もちろん、伝統文化に関する内容も必要だが、それだけにこだわってはいけないと思った。今の韓国人は笠をかぶり、韓屋で暮らし、韓服を着て生活しているわけではないから。そんなことだけを紹介しても、外国人に韓国を理解してもらえないと思った。だから、現在の韓国社会も簡単に紹介する必要があると思った。
‐タイトルは『スケッチ・オブ・コリア(Sketches of Korea)』だが、内容は「スケッチ」のような軽いものではない。詳細なところまで踏み込んでおり、むしろ重い内容だ。このタイトルにした理由は。
当初はビジュアル・ガイドブックのように軽い内容のものにしたかった。でも、制作しているうちに、イラストに簡単な説明を添えるだけではいけないと思うようになった。その結果、「ビジュアル+テキスト」の本になってしまった。しかし、この本は、決して学術的なエッセイではないと思う。きめ細かく描かれた絵画ではなく「スケッチ」なので、本のタイトルに相応しいと思った。韓国の奥深いところまで紹介するのではなく、韓国の代表的な要素がすべて盛り込まれているからだ。この本は、ガイドブックであって、堅苦しい学術論文ではない。
このところ韓国を訪れる外国人観光客が増えている。Kポップや韓国映画など韓国文化の一部に関心があって韓国を訪れる人は多い。しかし、私たちが言いたいのは「韓国は国である」ということだ。韓国は、Kポップ、映画、サムスン、サイ(PSY)、「江南スタイル」だけの国ではない。「深い歴史と多様な文化を持つ興味深い国」であることを紹介したかった。50年前、韓国といえば朝鮮戦争やソウル五輪など、簡単なことしか知ることができなかった。今はそれではいけないと思った。
海外では最近、韓国に関するドキュメンタリーが多く制作されている。だが、多くは済州島の海女や宮中料理、インサ(仁寺)洞の茶道文化、深夜まで塾を転々とする子どもたち、教育熱の高さなど、内容が限られているようだ。20年前なら理解できるかもしれないが、今はもっと踏み込んだ内容が必要だと思う。初対面の人に会ったとき、初めは名前や年齢など基本的なことしか聞いたり答えたりしないが、やがて友だちになって親しくなろうと思ったらもっと互いを深く知らなければならないように。この本は決して奥は深くないが、この本を通して韓国にアプローチすることはできる。韓国がビビンバや戦争、ソウル五輪、Kポップ、韓国映画、サムスン、PSY、「江南スタイル」だけの国ではないことを知り、韓国の民族や政治などにも関心を持ってほしいと思う。

- 飲酒文化や結婚式の祝儀金、銭湯で背中を流し合うことなど、韓国の特異な文化について説明している。それらを取り上げた基準とは。
もともとはシリーズとして月刊誌に寄稿するつもりだった。エロディさんと話し合って40ほどのテーマを決めた。そして、本の制作段階で編集者と話し合っていくつか修正した。その過程で編集者と意見が食い違い、妥協した部分もある。例えば、「コンミナム」や「フンナム」といった言葉だ。本の構想を考えていたときはそうした言葉がたくさん使われていたが、制作していくうちに使用頻度が少なくなったり、忘れられてしまったりした。また、定義が難しい言葉でもあった。「フンナム」という言葉に対するそれぞれの理解と定義は異なるが、大衆文化なので辞書には載っておらず、そんな些細なことで悩んだ。
こうした本の制作は、実は学術書籍よりも時間がかかるし、難しい。事実を一つひとつ確かめなければならないが、私たちが以前から当然だと思っていたことが実は当然ではなかったりすることが多いからだ。私は万物博士ではなく、専門知識もない。しかも韓国人でも知らないことが多く、多くの時間を費やした。
- 伝統や芸術に関する内容が特に細かく書かれている。韓国人でもわからない内容がかなりある。関連資料の収集は容易ではなかったと思うが。
特に苦労はしなかった。後に韓国学を専攻し、博士号を取得した。その過程で参考文献を手に入れる方法を知り、多くの関連資料を入手することができた。しかし、困難は別のところにあった。例えば、朝鮮時代の人々の服装でいうと、韓国人は「白衣の民族」なので白い服を着ているものだと多くの人は思っている。しかし、実際にはそうではない。朝鮮時代初頭には平民たちが白い服を着るのを何度か法で禁じた時期があった。白い服を着ていたのは両班(貴族階級)だけだった。しかし、これに相反する論文も存在する。色のついた服を平民は着てはならず、子ども、老人、両班しか着れなかったというのだ。セジョン(世宗)大王の時代にこうした法ができたという。では、「いったい韓国人は朝鮮時代にどんな色の服を着ていたのか」という疑問が湧いてくる。19世紀に韓国に渡った外国人の踏査記などには、韓国人はみな白い服を着る独特な民族だと記述されているが、これと一致しない学術論文も存在する。私はこの分野の専門家ではないので、この内容をどうするかは容易な問題ではなかった。例えば、14世紀と17世紀が異なるので各年代を確認する必要があったが、こうした内容を本で取り上げるには限界があった。朝鮮時代だけでなく、新羅時代と高麗時代もあり、韓国史をこうした本で取り上げるには無理があった。本を執筆しながら、もっと多くのことを学ぶ必要があると思った。同時に、これからこうした本をたくさん執筆する必要があるとも思った。
- 韓国で約20年暮らしているが、定着しようと思ったきっかけは。
初めて韓国に来たきっかけは、知人に勧められたからだ。当初は2年間滞在するつもりだったが、仕事が終わっても帰国せず、そのまま韓国にいることにした。そうしているうちに、滞在期間がどんどん延びていった。そのときも、韓国に定着しようとは思っていなかった。韓国に定着しようと思うようになったのは、10年ほど経ってレストラン事業を始めたときからだ。韓国で大学教授を務める外国人は、2~3年滞在したら自国に帰国するものだと思われていた。レストランを経営し、会社を立ち上げ、代表取締役になると、そのときから私は違う目で見られ、認めてもらっているような気がした。それで精神的に安定することができ、フランスに帰国しようとは思わなくなった。現在レストラン経営はしていないが、そのときに根を張ったおかげで韓国に定着できたと思う。 レストラン経営を始めたのは実は経済的な理由からだ。15年前は、外国人として教授を務めるには毎年契約を更新する必要があった。もちろん、制度的な理由もあった。自分の専攻分野を教えたかったし、経済的に独立する必要があると感じた。将来を見据えたとき、レストラン事業をすれば、ビザの発給が受けられ、自分が書きたい本を執筆することができ、研究も続けられると思った。
- 韓国生活で一番楽しかったことは。反対に一番辛かったことは。
どちらも同じ答えだ。外国で外国人として暮らすことだ。とても楽しく、おもしろく、興味深く、情熱に満ちた暮らしを送ることができている。しかし、西洋人として韓国で暮らすのは、「自分は韓国人ではない」という事実を毎日つきつけられているような気分だった。あと2~3年でフランスよりも韓国で暮らした時間のほうが長くなる。自分のアイデンティティの一部は‘韓国ナイズ’されたようだ。フランス人でありながら、多文化人になってしまったようだ。自分が複合的なアイデンティティを持っていることを楽しい気持ちで発見した。同時に、それは辛く苦しい過程だった。韓国人になれる方法はまだないと思うときもある。法的な問題もある。それらの問題は解決できるかもしれないが、もっと重要なのは文化的な問題だ。韓国に必要なことは、私のような西洋人も韓国人として受け入れる文化的準備だと思う。次の世代にはもっと変わっているだろう。実際、韓国人が外国で暮らしても同じことを感じると思う。国によって違ってくる部分もあるだろうし。
ある意味、異邦人でも邦人でもない曖昧な立場で暮らしているような感覚だ。その立場で暮らすのは容易なことだけではない。しかし、これが自分の運命、定めだと思い、喜びの気持ちで前向きに受け入れている。ちょうど10年前、そんな気持ちになり、今の立場でも幸せに暮らしていけると思った瞬間、もうフランスには戻らないと決心した。
- 韓国で生活しながら、これには共感できないとか、特異に感じた文化やライフスタイルとは。
‐韓国で生活しながら、これには共感できないとか、特異に感じた文化やライフスタイルとは。韓国に来たばかりの頃は、特異に感じられることが多くあったが、今はそうではない。暮らしているうちに慣れていった。しかし、理解できないわけではないが、残念に思うことはある。韓国人はもっと余裕を持って生活してほしいと思う。余裕とは休暇だけを意味するのではない。より抽象的な概念だ。言い換えれば、主体と対象、自分のすることとの適切な距離、つまり心理的な空間が必要だということだ。このところ韓国では創造を強調する人が多い。経済発展につながるクリエイティブな思考を生むためには、精神的(mental)な余裕が必要だと思う。学生であれ、会社員であれ、家と学校、家と職場を毎日往復するだけの生活パターンから、果たしてクリエイティブなアイデアが生まれるだろうか。韓国人は仕事だけでなく、機関にも縛られすぎているようで残念に思う。それは全く生産的ではないと思う。
- あなたの本を読めば、韓国の文化と芸術への愛情が読み取れる。特に魅了された韓国の文化、または芸術とは。
個人的に民画が好きだ。民画は日本による植民統治期に日本人によって生まれたもので、19世紀以前はただ「多様な絵画」としてみなされていた。民画の多様性が気に入っている。朝鮮末期の庶民の絵画などが好きで、庶民がお守りとして作った作品を所蔵している。秘められたシンボルがたくさんありそうで、魅力的で興味深い。いつも家で楽しく鑑賞している。日常的で単純な絵でありながら、何か無意識的かつ普遍的な特徴を持っているようだ。韓国人でなくても見れば見るほど何か感じることがある。一枚の壁に様々な作品をかけて鑑賞している。ほとんどが19世紀末~20世紀初頭の興味深い作品だ。

- 海外の知人にぜひ紹介したい韓国文化は。
今住んでいる場所はイヌァン(仁王)山の麓のヒョジャ(孝子)洞ソチョン(西村)だ。私が住んでいる地域には韓国に関するすべてのものがあると思う。外国にいる友人が韓国を訪ねてきたら、その町に連れていく。市内や自然、山、街、田舎、昔、現在、楽しい食い倒れ横丁、飲み会、美味しい飲食店、韓屋、市場など、すべてのものがあるからだ。遠くまで行く必要はない。韓国らしい生きたエネルギーを感じることができる。外国人はみんなそうした面を好む。そして、チョンラ(全羅)道のような田舎の韓屋ペンションや宗家などに宿泊することもおすすめしたい。
- 人文学、哲学から文化人類学、韓国学に専攻を変え、現在はフランス・レストランを経営する傍ら、展示企画者、フード・コラムリスト、グルメ番組の司会者としても活動している。特に印象的なのはフランスと韓国の料理に対する関心だ。食文化に注目するようになったきっかけは。
個人的には、韓国の食文化を外国人に紹介する番組の司会を務めたことが記憶に残っている。各地域の田舎を訪問して韓国の食文化を紹介・説明する番組だったが、とても楽しかった。 飲食物は学界において未だにあまり高く評価されていないようで残念だ。恐らく、日常的な暮らしの一部なので、取るに足らないものと見られ、人文学的な研究テーマとして取り上げられないのかもしれない。それは矛盾だ。飲食物は私たちが毎日摂取するものであって、そうしなければ苦痛だ。歴史的に見ても、革命は食糧問題から始まっていることが多い。クロード・レヴィ=ストロース(Claude Levi Strauss、1908~2009)の場合もそうだが、人類学研究において食文化に関する学習は基本だ。飲食物が高く評価されていないことを残念に思う。フランスの学界では、1960年代から日常生活を再発見しようという動きがあった。そうした研究は非常に興味深いと思う。控えめなテーマだが、研究すれば無限かつ深みのある文化的研究ができる。飲食物を通して韓国についてもっと学べると思う。飲食物を理解すれば、韓国文化のすべてを知ることができる。食べ物が嫌いで関心がないという人はいないからだ。そうした観点から、飲食物でいくらでも外国人の関心を引くことができると思う。そうして少しずつ深みにはまっていく。まるで罠(trap)のようだ。
- 韓国フードの発信に熱意を見せているが、一番好きな韓国フードは。
たくさんあり過ぎて一つだけ挙げるのは難しい。状況によっても違ってくる。春の雨の降る日に友人と一緒に食べたいもの、寒い冬に食べたいもの、一人でいるときに食べたいもの、それぞれ違う。全般的にどれも好きだから。システムも味もすべて気に入っている。韓国フードという制度を体で理解しているので、何でも好きだ。華やかな宮中料理や素敵な器で出されなくても、美味しいおかずとご飯、汁物というありふれたペクパン(白飯)も何でも好きだ。一時期ごま油が嫌になったことがあるが、韓国フードに慣れるまで時間がかかっただけで、もうそんなことはなくなった。これも余裕と関係がある。韓国フードのグローバル化も、同じ観点から慣れには余裕が必要だと思う。韓国フードを体で理解するには時間が必要だ。
- 韓国とフランスは異質な面もあるが、共有できることも多いと思う。実際に韓国ではフランスの文学や哲学、料理、ファッションなど文化全般にわたって関心が高い。文化人類学者の観点から両国の文化交流のあり方とは。
方法はよくわからないが、両国の文化交流が活性化することを心から願っている。韓国とフランスは似ていることが多い。フランスも韓国と同様に、訪問してすぐ魅力を感じる国ではないと思う。もちろん、パリにもKポップのようなイメージがあるが、夢中になるまでには時間がかかる。一度夢中になれば、好きで好きでたまらなくなる。それがフランスだ。理解するのは難しいかもしれない。魅力を感じるには時間がかかり、理解が複雑な国なのだが、時間が必要だと思う。しかし、一度魅力を感じれば感情は長く続く。
- 今後、ぜひしてみたいことは。
執筆と研究活動に集中したい。韓仏交流関連の活動も続けるつもりだ。
コリアネット ユン・ソジョン記者
写真:コリアネット チョン・ハン記者
arete@korea.kr
韓国在住20年目でホンイク(弘益)大学教授のベンジャミン・ジュアノ(Benjamin Joinau)さんが執筆し、エロディ・ドルナン・ド・ルーヴィル(Elodie Dornand de Rouville)さんがイラストを担当した『スケッチーズ・オブ・コリア(Sketches of Korea)』だ。
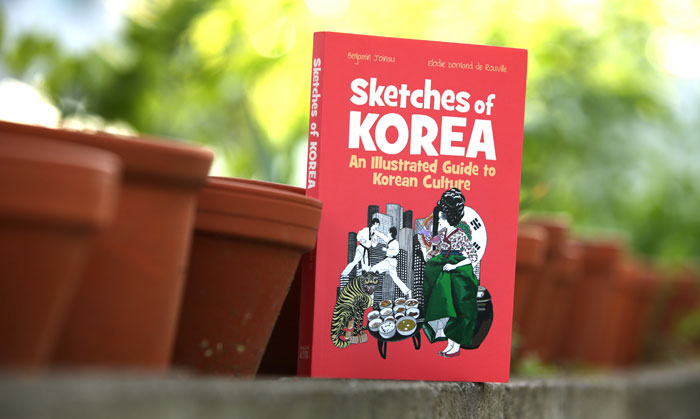

韓国紹介書『スケッチーズ・オブ・コリア』を制作したジュアノさん(右)とルーヴィルさん(左)
同書は、韓国の飲酒文化や爆弾酒(アルコール度数の高いウィスキーや焼酎をビールに混ぜたもの)、慶弔事の祝儀金と香典、銭湯で知らない人同士で背中を流し合うことなど、外国人がほとんど目にしない風景に注目している。また、「フンナム」(温かい雰囲気の男性)や「コンミナム」(イケメン)といった言葉を紹介しながら韓国社会の外見至上主義について説明する。
著者のジュアノさんは、現代だけでなく、伝統と芸術、韓国フードについても、イラストを交えながら事実に基づいて説明している。特に、キムチのレシピと歴史について紹介し、「フランスではバゲット、イタリアではパスタのように、キムチは韓国民族の遺産(national heritage)で万能薬(panacea)のようなもの」と論じる。伝統芸術では、山水画や風俗画、古家具など、韓国人もあまり知らないことについても紹介している。
ジュアノさんの目に映る韓国の社会と文化、そして韓国とフランスに対する思いについてインタビューした。

韓国の現実的な文化と社会を紹介しようと『スケッチ・オブ・コリア』を執筆したというジュアノさん
‐『スケッチ・オブ・コリア』を執筆しようと思った動機は。
韓国で暮らし始めて約20年になるが、当時は外国語で書かれた韓国に関する本、特にフランス語で書かれた本はほとんどなかった。それで、韓国に来る準備にとても苦労した。実際に韓国に来て道に迷うことが多く、それ以上にカルチャーショックが大きかった。もちろん、謎解きのような楽しさもあった。しかし、私のように韓国を体験した一部の人を除き、暇のないほとんどの人には資料があまりにも少なすぎると思った。
1998年にフランスの某出版社とともに韓国の旅行ガイドブックを出版した。私が初めて執筆した韓国に関する本だ。その本もある程度有用だとは思ったが、単なる道案内だけでなく、目的地にたどり着くために必要な文化的知識を紹介することが必要だと思った。その本を執筆する6~7年前にも書店に行けば英語で書かれた韓国紹介書はあったが、それでは不十分だと思った。 いくら本のデザインがきれいでも、ほとんどが韓国人の目から見た本だったからだ。内容のほとんどが外国人の見方と一致しないものが多く、外国人を対象にしてはいるものの韓国人が一番良いと思うものを紹介しているものばかりだった。例えば、メドゥプ(朝鮮半島に伝わる飾り結び)やポデギ(おんぶ紐)などは、韓国らしいものだが、歴史的・文化的な深みがないと思った。そうした本は、見かけはきれいでも、あまり役に立たない「コーヒーテーブル・ブック」に過ぎない。だから、本の構想についてエロディさんと話し合い、多くの人は本を読むとき、文字よりも先に絵を見るので、イラストを入れたほうが効果的だという意見で一致した。人は誰でも視覚的なもののほうに先に目がいくのだから。それで私たちは、「イラストで見る韓国の本」を制作することにした。
次に、朝鮮時代末期の韓国ではなく、私たちが日常的に目にする現在の韓国の姿を見せ、説明する必要があると思った。もちろん、伝統文化に関する内容も必要だが、それだけにこだわってはいけないと思った。今の韓国人は笠をかぶり、韓屋で暮らし、韓服を着て生活しているわけではないから。そんなことだけを紹介しても、外国人に韓国を理解してもらえないと思った。だから、現在の韓国社会も簡単に紹介する必要があると思った。
‐タイトルは『スケッチ・オブ・コリア(Sketches of Korea)』だが、内容は「スケッチ」のような軽いものではない。詳細なところまで踏み込んでおり、むしろ重い内容だ。このタイトルにした理由は。
当初はビジュアル・ガイドブックのように軽い内容のものにしたかった。でも、制作しているうちに、イラストに簡単な説明を添えるだけではいけないと思うようになった。その結果、「ビジュアル+テキスト」の本になってしまった。しかし、この本は、決して学術的なエッセイではないと思う。きめ細かく描かれた絵画ではなく「スケッチ」なので、本のタイトルに相応しいと思った。韓国の奥深いところまで紹介するのではなく、韓国の代表的な要素がすべて盛り込まれているからだ。この本は、ガイドブックであって、堅苦しい学術論文ではない。
このところ韓国を訪れる外国人観光客が増えている。Kポップや韓国映画など韓国文化の一部に関心があって韓国を訪れる人は多い。しかし、私たちが言いたいのは「韓国は国である」ということだ。韓国は、Kポップ、映画、サムスン、サイ(PSY)、「江南スタイル」だけの国ではない。「深い歴史と多様な文化を持つ興味深い国」であることを紹介したかった。50年前、韓国といえば朝鮮戦争やソウル五輪など、簡単なことしか知ることができなかった。今はそれではいけないと思った。
海外では最近、韓国に関するドキュメンタリーが多く制作されている。だが、多くは済州島の海女や宮中料理、インサ(仁寺)洞の茶道文化、深夜まで塾を転々とする子どもたち、教育熱の高さなど、内容が限られているようだ。20年前なら理解できるかもしれないが、今はもっと踏み込んだ内容が必要だと思う。初対面の人に会ったとき、初めは名前や年齢など基本的なことしか聞いたり答えたりしないが、やがて友だちになって親しくなろうと思ったらもっと互いを深く知らなければならないように。この本は決して奥は深くないが、この本を通して韓国にアプローチすることはできる。韓国がビビンバや戦争、ソウル五輪、Kポップ、韓国映画、サムスン、PSY、「江南スタイル」だけの国ではないことを知り、韓国の民族や政治などにも関心を持ってほしいと思う。

韓国の断片的な内容ではなく、文化的・社会的な面を幅広く紹介することが必要だと強調するジュノアさん
- 飲酒文化や結婚式の祝儀金、銭湯で背中を流し合うことなど、韓国の特異な文化について説明している。それらを取り上げた基準とは。
もともとはシリーズとして月刊誌に寄稿するつもりだった。エロディさんと話し合って40ほどのテーマを決めた。そして、本の制作段階で編集者と話し合っていくつか修正した。その過程で編集者と意見が食い違い、妥協した部分もある。例えば、「コンミナム」や「フンナム」といった言葉だ。本の構想を考えていたときはそうした言葉がたくさん使われていたが、制作していくうちに使用頻度が少なくなったり、忘れられてしまったりした。また、定義が難しい言葉でもあった。「フンナム」という言葉に対するそれぞれの理解と定義は異なるが、大衆文化なので辞書には載っておらず、そんな些細なことで悩んだ。
こうした本の制作は、実は学術書籍よりも時間がかかるし、難しい。事実を一つひとつ確かめなければならないが、私たちが以前から当然だと思っていたことが実は当然ではなかったりすることが多いからだ。私は万物博士ではなく、専門知識もない。しかも韓国人でも知らないことが多く、多くの時間を費やした。
- 伝統や芸術に関する内容が特に細かく書かれている。韓国人でもわからない内容がかなりある。関連資料の収集は容易ではなかったと思うが。
特に苦労はしなかった。後に韓国学を専攻し、博士号を取得した。その過程で参考文献を手に入れる方法を知り、多くの関連資料を入手することができた。しかし、困難は別のところにあった。例えば、朝鮮時代の人々の服装でいうと、韓国人は「白衣の民族」なので白い服を着ているものだと多くの人は思っている。しかし、実際にはそうではない。朝鮮時代初頭には平民たちが白い服を着るのを何度か法で禁じた時期があった。白い服を着ていたのは両班(貴族階級)だけだった。しかし、これに相反する論文も存在する。色のついた服を平民は着てはならず、子ども、老人、両班しか着れなかったというのだ。セジョン(世宗)大王の時代にこうした法ができたという。では、「いったい韓国人は朝鮮時代にどんな色の服を着ていたのか」という疑問が湧いてくる。19世紀に韓国に渡った外国人の踏査記などには、韓国人はみな白い服を着る独特な民族だと記述されているが、これと一致しない学術論文も存在する。私はこの分野の専門家ではないので、この内容をどうするかは容易な問題ではなかった。例えば、14世紀と17世紀が異なるので各年代を確認する必要があったが、こうした内容を本で取り上げるには限界があった。朝鮮時代だけでなく、新羅時代と高麗時代もあり、韓国史をこうした本で取り上げるには無理があった。本を執筆しながら、もっと多くのことを学ぶ必要があると思った。同時に、これからこうした本をたくさん執筆する必要があるとも思った。
- 韓国で約20年暮らしているが、定着しようと思ったきっかけは。
初めて韓国に来たきっかけは、知人に勧められたからだ。当初は2年間滞在するつもりだったが、仕事が終わっても帰国せず、そのまま韓国にいることにした。そうしているうちに、滞在期間がどんどん延びていった。そのときも、韓国に定着しようとは思っていなかった。韓国に定着しようと思うようになったのは、10年ほど経ってレストラン事業を始めたときからだ。韓国で大学教授を務める外国人は、2~3年滞在したら自国に帰国するものだと思われていた。レストランを経営し、会社を立ち上げ、代表取締役になると、そのときから私は違う目で見られ、認めてもらっているような気がした。それで精神的に安定することができ、フランスに帰国しようとは思わなくなった。現在レストラン経営はしていないが、そのときに根を張ったおかげで韓国に定着できたと思う。 レストラン経営を始めたのは実は経済的な理由からだ。15年前は、外国人として教授を務めるには毎年契約を更新する必要があった。もちろん、制度的な理由もあった。自分の専攻分野を教えたかったし、経済的に独立する必要があると感じた。将来を見据えたとき、レストラン事業をすれば、ビザの発給が受けられ、自分が書きたい本を執筆することができ、研究も続けられると思った。
- 韓国生活で一番楽しかったことは。反対に一番辛かったことは。
どちらも同じ答えだ。外国で外国人として暮らすことだ。とても楽しく、おもしろく、興味深く、情熱に満ちた暮らしを送ることができている。しかし、西洋人として韓国で暮らすのは、「自分は韓国人ではない」という事実を毎日つきつけられているような気分だった。あと2~3年でフランスよりも韓国で暮らした時間のほうが長くなる。自分のアイデンティティの一部は‘韓国ナイズ’されたようだ。フランス人でありながら、多文化人になってしまったようだ。自分が複合的なアイデンティティを持っていることを楽しい気持ちで発見した。同時に、それは辛く苦しい過程だった。韓国人になれる方法はまだないと思うときもある。法的な問題もある。それらの問題は解決できるかもしれないが、もっと重要なのは文化的な問題だ。韓国に必要なことは、私のような西洋人も韓国人として受け入れる文化的準備だと思う。次の世代にはもっと変わっているだろう。実際、韓国人が外国で暮らしても同じことを感じると思う。国によって違ってくる部分もあるだろうし。
ある意味、異邦人でも邦人でもない曖昧な立場で暮らしているような感覚だ。その立場で暮らすのは容易なことだけではない。しかし、これが自分の運命、定めだと思い、喜びの気持ちで前向きに受け入れている。ちょうど10年前、そんな気持ちになり、今の立場でも幸せに暮らしていけると思った瞬間、もうフランスには戻らないと決心した。
- 韓国で生活しながら、これには共感できないとか、特異に感じた文化やライフスタイルとは。
‐韓国で生活しながら、これには共感できないとか、特異に感じた文化やライフスタイルとは。韓国に来たばかりの頃は、特異に感じられることが多くあったが、今はそうではない。暮らしているうちに慣れていった。しかし、理解できないわけではないが、残念に思うことはある。韓国人はもっと余裕を持って生活してほしいと思う。余裕とは休暇だけを意味するのではない。より抽象的な概念だ。言い換えれば、主体と対象、自分のすることとの適切な距離、つまり心理的な空間が必要だということだ。このところ韓国では創造を強調する人が多い。経済発展につながるクリエイティブな思考を生むためには、精神的(mental)な余裕が必要だと思う。学生であれ、会社員であれ、家と学校、家と職場を毎日往復するだけの生活パターンから、果たしてクリエイティブなアイデアが生まれるだろうか。韓国人は仕事だけでなく、機関にも縛られすぎているようで残念に思う。それは全く生産的ではないと思う。
- あなたの本を読めば、韓国の文化と芸術への愛情が読み取れる。特に魅了された韓国の文化、または芸術とは。
個人的に民画が好きだ。民画は日本による植民統治期に日本人によって生まれたもので、19世紀以前はただ「多様な絵画」としてみなされていた。民画の多様性が気に入っている。朝鮮末期の庶民の絵画などが好きで、庶民がお守りとして作った作品を所蔵している。秘められたシンボルがたくさんありそうで、魅力的で興味深い。いつも家で楽しく鑑賞している。日常的で単純な絵でありながら、何か無意識的かつ普遍的な特徴を持っているようだ。韓国人でなくても見れば見るほど何か感じることがある。一枚の壁に様々な作品をかけて鑑賞している。ほとんどが19世紀末~20世紀初頭の興味深い作品だ。

韓国に定着することが「定め」と思い、運命を前向きに受け入れたと語るジュアノ氏
- 海外の知人にぜひ紹介したい韓国文化は。
今住んでいる場所はイヌァン(仁王)山の麓のヒョジャ(孝子)洞ソチョン(西村)だ。私が住んでいる地域には韓国に関するすべてのものがあると思う。外国にいる友人が韓国を訪ねてきたら、その町に連れていく。市内や自然、山、街、田舎、昔、現在、楽しい食い倒れ横丁、飲み会、美味しい飲食店、韓屋、市場など、すべてのものがあるからだ。遠くまで行く必要はない。韓国らしい生きたエネルギーを感じることができる。外国人はみんなそうした面を好む。そして、チョンラ(全羅)道のような田舎の韓屋ペンションや宗家などに宿泊することもおすすめしたい。
- 人文学、哲学から文化人類学、韓国学に専攻を変え、現在はフランス・レストランを経営する傍ら、展示企画者、フード・コラムリスト、グルメ番組の司会者としても活動している。特に印象的なのはフランスと韓国の料理に対する関心だ。食文化に注目するようになったきっかけは。
個人的には、韓国の食文化を外国人に紹介する番組の司会を務めたことが記憶に残っている。各地域の田舎を訪問して韓国の食文化を紹介・説明する番組だったが、とても楽しかった。 飲食物は学界において未だにあまり高く評価されていないようで残念だ。恐らく、日常的な暮らしの一部なので、取るに足らないものと見られ、人文学的な研究テーマとして取り上げられないのかもしれない。それは矛盾だ。飲食物は私たちが毎日摂取するものであって、そうしなければ苦痛だ。歴史的に見ても、革命は食糧問題から始まっていることが多い。クロード・レヴィ=ストロース(Claude Levi Strauss、1908~2009)の場合もそうだが、人類学研究において食文化に関する学習は基本だ。飲食物が高く評価されていないことを残念に思う。フランスの学界では、1960年代から日常生活を再発見しようという動きがあった。そうした研究は非常に興味深いと思う。控えめなテーマだが、研究すれば無限かつ深みのある文化的研究ができる。飲食物を通して韓国についてもっと学べると思う。飲食物を理解すれば、韓国文化のすべてを知ることができる。食べ物が嫌いで関心がないという人はいないからだ。そうした観点から、飲食物でいくらでも外国人の関心を引くことができると思う。そうして少しずつ深みにはまっていく。まるで罠(trap)のようだ。
- 韓国フードの発信に熱意を見せているが、一番好きな韓国フードは。
たくさんあり過ぎて一つだけ挙げるのは難しい。状況によっても違ってくる。春の雨の降る日に友人と一緒に食べたいもの、寒い冬に食べたいもの、一人でいるときに食べたいもの、それぞれ違う。全般的にどれも好きだから。システムも味もすべて気に入っている。韓国フードという制度を体で理解しているので、何でも好きだ。華やかな宮中料理や素敵な器で出されなくても、美味しいおかずとご飯、汁物というありふれたペクパン(白飯)も何でも好きだ。一時期ごま油が嫌になったことがあるが、韓国フードに慣れるまで時間がかかっただけで、もうそんなことはなくなった。これも余裕と関係がある。韓国フードのグローバル化も、同じ観点から慣れには余裕が必要だと思う。韓国フードを体で理解するには時間が必要だ。
- 韓国とフランスは異質な面もあるが、共有できることも多いと思う。実際に韓国ではフランスの文学や哲学、料理、ファッションなど文化全般にわたって関心が高い。文化人類学者の観点から両国の文化交流のあり方とは。
方法はよくわからないが、両国の文化交流が活性化することを心から願っている。韓国とフランスは似ていることが多い。フランスも韓国と同様に、訪問してすぐ魅力を感じる国ではないと思う。もちろん、パリにもKポップのようなイメージがあるが、夢中になるまでには時間がかかる。一度夢中になれば、好きで好きでたまらなくなる。それがフランスだ。理解するのは難しいかもしれない。魅力を感じるには時間がかかり、理解が複雑な国なのだが、時間が必要だと思う。しかし、一度魅力を感じれば感情は長く続く。
- 今後、ぜひしてみたいことは。
執筆と研究活動に集中したい。韓仏交流関連の活動も続けるつもりだ。
コリアネット ユン・ソジョン記者
写真:コリアネット チョン・ハン記者
arete@korea.kr