| 小説家・黃晳暎(ファン・ソギョン)の作品『パリデギ』は親に捨てられたパリ公主(王女)説話を現代風に置き換えたもの。難民、不法滞在、大都市集中現象など現代社会が抱える問題を取り上げている。 |
現実と幻想の間のどこかに転移点がある。それは7世代に渡って繰り返される歴史のなかに存在する。一方で空を飛ぶグリフォン(鷲の翼と上半身、ライオンの下半身をもつ伝説上の生物)や魔法の呪文はその彼方にある。いつからこれら「魔術的リアリズム」がファンタジーになったのだろう。南米文学の巨匠、コロンビアのガブリエル・ガルシア=マルケスとジョアン・ローリングの間に黃晳暎の『パリデギ』が位置している。
そこには幽霊やシャーマン、魂、腸チフスで死んだ子供たちが登場する。シロという名の犬は人間のように振舞う。魔女と鬼、薄暗いお寺もある。彼女は犬のチルソンや耳と口が不自由な姉とテレパシーで話す。死んだ親戚と会話し、あの世の彼らを見ることができる。足裏の色だけでお客の健康状態を読み取れる。彼女は魂を理解し、魂を癒すことができる。
お祖母さんが言ったように「パリの才能は生まれつき」のものだ。
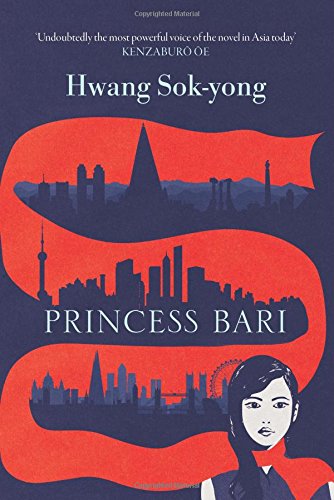
2007年に発刊した黃晳暎の『パリデギ』は2015年に英語版が出版された
韓国の説話に、捨てられた王女の物語『パリ公主』がある。パリ公主は男の子を望むオグィ大王の末っ子の第7子として生まれるが、娘であるがゆえに生まれてすぐ捨てられてしまう。黄泉に行った彼女は不老不死の薬(生命水)を手に入れ、新しい世界に生まれ変わる。そしてステュクス川で死者の魂を運ぶカーロンのように死者をあの世へと導くオグ神になる。
ローマの詩人ウェルギリウス(70 B.C.-19 B.C.)は大叙事詩の『アエネーイス』をB.C.29~B.C.19頃に書いた。同作はアエネーアースというトロイアの戦士が滅びた都市を離れ地中海を渡りローマを建設するストーリーとなっている。イタリアの作家ボッカッチョ(1313~1375)は14世紀後半に短編小説の『デカメロン』を書いた。フィレンツェの古典といわれる同作では10本の短編に登場する10人の人物が黒死病を避けて都市の外れに避難する。
2007年に発表された黃晳暎の『パリデギ』は、これらの作品と似ている。『パリデギ』は旅立ちの物語である。同作は全体主義国家による恐怖から逃げたある巫女が、中国の吉林省と遼寧省で難民生活を強いられ、世界を回った末ロンドンに辿りつく過程を描いている。
作中の「パリ公主」の運命は歴史の記録に登場する多くの女性のそれに似ている。苦難を経験し、女性として「望ましい姿」を期待される世界を生きる女性たち。我々が生きるこの世の中にも親の行動や期待に苦しむ多くのパリ公主がいる。社会が彼らに自由や身動きできる余裕を与えなかったため自らを犠牲にするしかなかった数多くのパリデギ。社会の罠にはめられ苦しみ、献身し、ぎ然としてその苦しみに耐えることを強いられる。
パリ公主は父王の命を救うために自分の命を犠牲にする。これこそ家父長主義の社会が女性に期待するものである。この世の限界を超えて超越した人間になるために自らを犠牲にし苦しみに耐えるパリ公主はすべての女性の英雄である。彼女は世界を癒す。それになんと犬とコミュニケーションできる能力すら持っている。
古くからの説話をベースにしたこの作品で作家は(説話のパリ公主と同様)第7子として生まれたヒロインが経験する事件を1本の美しい物語に編み上げ読者を引き込む。主人公は貧しく飢えている抑圧された全体主義国家の北韓から中国の吉林省、東アジア一1美しい自然の港といわれる遼寧省に、そして大洋を渡りイギリスのロンドンへと移る。この過程で主人公は人間としての成長を遂げ、暖かく、お祖母さんのように愛情を与える方法を教わる。そして世の中の傷を癒す。未来が分かる人間として、そして巫女として、彼女は顧客の病気を理解して何が間違っているのかを把握することによりその回復を助ける。動物やすでに死んだり行方不明になった親戚(生死に関わらず)と会話をする。説話のパリ公主が不老不死の薬を手に入れたようにパリは我々の傷を優しく撫でてくれる。
「大連で私たちは希望に満ちていた。美しい海辺ときれいな都心、公園はどれだけ上手に手入れされていたものか」 (第5章中)
黃晳暎が小説の背景として選んだ北韓の現実は1970年代のルーマニアより深刻な、残酷なものだった。
「洪水で氾濫した野原と都市の外れには多くの死体がぷかぷか浮かんでいた」(第3章中)
作家は作品から南北関係の改善を強く支持してきた。実際数回に渡り北韓を訪問していた彼は、それを理由に刑務所に収監されたこともある。釈放から数年後、ようやく執筆を再開した。その時期に書いたのが『パリデギ』である。
「配給も途絶え、労賃も支給されなかったため鉱員たちも仕事を止め食料を求めて彷徨い始めた。地方の大小の工場は廃業したり、操業を止めたところが少なくなかった」(第2章中)
同作が発表されたのは2007年だが、英語版は2015年に発刊された。翻訳はソラ・キム・ラッセル(Sora Kim-Russell)が担当した。現在この英語版はイギリスでのみ購入できる。(日本語版は青柳優子の翻訳で岩波書店が2008年に出版)
1943年生まれの黃晳暎は2007年に小説『パリデギ』を発刊した。南北関係の改善を強く指示してきた彼は、北韓を訪問したことで1993年から1998年にかけて刑務所に収監された
『パリデギ』は単に1人の女性の物語ではない。家父長の社会に抵抗する女性の声を反映している。説話の『パリ公主』、そして黃晳暎の小説『パリデギ』で表れたように、シャーマニズムは社会全般に蔓延している男性優越主義を批判する。説話でも小説でも「パリ公主」のストーリーは作家と読者両方に関わる問題だ。男性優越主義に苦しむのは女性であるためだ。
黃晳暎と説話はいずれも世俗的世界に捕らわれずこの世の限界を超える女性のキャラクターを作り上げた。パリ公主はこの世が与える即時的報償を越え、厳しい儒教社会の向こう側にある神聖なる報償を選んだ。彼女は良妻賢母で従順な娘を、女性を判断する唯一の基準とする儒教主義社会の限界を超える女性のお手本であり、世界を癒すことができる存在である。
パリ公主は世界のすべての女性に語りかける。この社会が女性に期待するところを超えて、違う道を自ら選択しろと。パリ公主は自分をより良い人間に成長させなければならない現実に馴染んでいくが、だからといってそれに押しつぶされることはない。女性の尊厳を認めてもらうための戦いを諦めない。
最後に要約すると、小説『パリデギ』は説話にふさわしいお祖母さんと不思議な能力をもつ少女の人生を描いた物語である。彼女は祖母から受け継いだ才能を活かして世界へと進む。犬とはテレパシーで話し、地球とも調和を成す。彼女は魂を理解し、その魂を癒す。
コリアネット グレゴリー・イーヴス記者
写真:韓国文学翻訳院
翻訳:コリアネット ソン・ジエ、イム・ユジン
gceaves@korea.kr
