新石器時代の磨製石器、青銅器時代の石鏃、現代の韓国人が使う匙や箸、花札、ジーンズ…。
これらはどれも国立民俗博物館が所蔵する遺物で、ホームページで一目で検索できる資料だ。
国立民俗博物館は昨年11月、所蔵遺物の99%にあたる68,000点余りの飼料をすべて一般に公開した。最近では、グーグルの美術プログラム(Fine Arts Program)から資料活用協力(MOU)の提案もあった。所蔵品の大々的な公開は、世界的にも国立民俗博物館が初めてだからだ。ここには、千鎮基(チョン・ジンギ)館長の信念が込められている。
チョン館長の信念は博物館の情報化だけでなく、博物館の展示や役割に対する考えからも窺える。コリアネットは、チョン館長に博物館の進むべき道と民俗・文化・歴史についての考えを尋ねた。
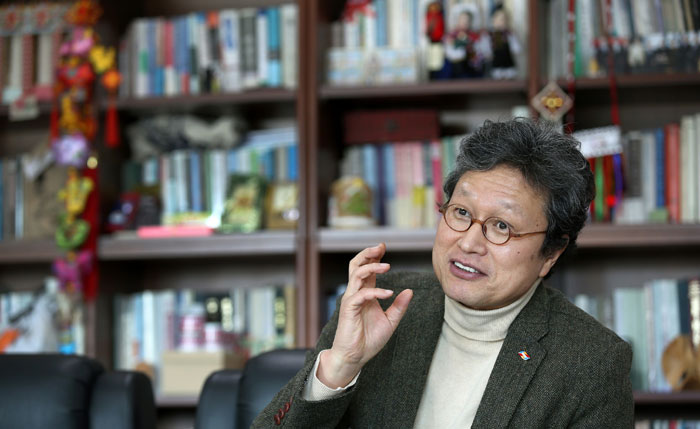
- 日常生活から国家間の交流にいたるまで展示の幅が広くなった。従来の「民俗」という概念を超えているように思えるが、どのような背景があるのか。
現在展示中の「飯膳の交わり」や「ジーンズ」などに次いで、再来年には「ジャンク(junk、ゴミ)」展も行う予定だ。この展示が成立し得るのは「民俗」の幅が広いからだ。また、国立民俗博物館は3年に一度は現代の世に強いメッセージを投げかけるべきだと考えている。
「ジーンズ」展は、英国のある人類学者のジーンズに関する報告書からアイディアを得た。その後、リーバイスの博物館に訪れたり、国内のアパレルメーカー「BANG BANG」などの歴史を顧たりと3年間に渡って調査をした。ジーンズをセクシーだと考える米国の80代の寄贈者の考え方とライフスタイル、1本500万円を上回る日本のプレミアムジーンズなど、皆が共感を抱ける「ジーンズ」という共通のアイテムであっても互いに異なる視点があるということがわかった。一方で、「飯膳の交わり」では空間・映像・音響など様々な分野におけるキュレーターやプロデューサーらの参加の下アイデアを構成し、360度回転可能な映像など新しい試みにも挑んだ。

- 文化生産者は増える反面、消費者は伸び悩んでいるようだ。原因と対策を伺いたい。
多くの人々が博物館の利用方法を知らないがために、単に勉強だけが目的となっている。このように文化生産者によって生産される文化の総量に比べて、文化の利用方法に対する消費者の知識が足りないのが原因ではないだろうか。文化生産者には、生産する前にできるだけ消費者の立場で考える配慮が求められる。
「猿のお尻は赤い」展を例に挙げるなら、母猿が小猿を抱いている青磁母子猿形硯滴を単に「青磁、猿の親子、硯滴」と捉えるのではなく、この遺物を見ながら涙することができなくてはならない。幼い子供を亡くした方、両親を亡くした方はこの遺物をみて涙しながら慰めを得られる思う。作品に家族愛と母性愛が込められているからだ。涙を流し慰めを得ることで心にゆとりができると、今度は猿や青磁の色にも目が行くようになる。そうすれば、その遺物を目ではなく心で感じることができる。こうなるためには博物館が心地よい場所でなければならない。単に知識を得るために博物館に訪れるのではなく、食べるために、遊ぶために来てもらえるようにしなくてはならないのだ。博物館を通して、人々の歴史と文化を見る観点と博物館に対する認識が変わることを期待したい。
- 国立民俗博物館は2010年からベトナム、モンゴル、フィリピン、ウズベキスタン、韓国、中国の文化を紹介する「多文化の箱」事業を運営中だ。異文化研究事業を続けるうえで追求している点はあるか。
文化は両方向からの疎通が必要だ。韓国の文化を発信するだけでなく、他の文化についても視野を広げ、人類が如何に共に調和をなして共存共栄するかを考えなくてはならない。そこで文化的なアプローチが一つの方法になり得るのではないだろうか。その延長線上で祖国と民族、人類の共存のために国立民俗博物館ができることの一つが「多文化の箱」事業なのだと思う。もとより、この事業の趣旨は異文化を共有し理解を広めることだった。
まずは、多文化に対する認識を変える必要がある。韓国の観点からのみ考えるのではなく、相手の立場になって考えなければならない。ベトナム人の嫁に韓国の文化を強要するのではなく、ベトナムの文化・言語などを少しずつ理解し分かち合えば、家族全員が幸せになれると思う。
韓・日・中3国はいずれも箸を使うが、形も素材もまちまちだ。各々の食文化があるからだ。この違いを変に捉えるのではなく、互いに理解しなければならない。文化に対する理解を通して人類愛を育むために、このような事業や比較展示を行ってきた。

我々は大量生産・消費の時代を生きている。例えば、大型スーパーで取り扱う品数は3~4万種類にも上るそうだが、この中から何かを買うとする。しかし、それを媒介に共有する空間・ヒト・モノが融合しなければ何の意味も成せないのである。現代の遺物を収集するうえで、博物館では家庭における所帯道具が全部で何個かを一つひとつチェックする。この調査を経て「所帯道具」のカタログを年に3回作っている。遺物カードのように数や種類、位置情報などをすべて調査して写真を撮って記録する形だ。この過程で寄贈を募集することもある。そうすると後々その家をそのまま再現することもできる。このように文化的な状況の中に入り込んだ遺物、つまり使った人・時期・場所のデータがあるもは所蔵価値があると判断できる。今すぐはそうでなくても、10年後には意味のあるものとなるのだ。
「今」をどのように記録して収集するのか、また将来どうやって再現するのかについて考えなければならない。これは、我々が貝塚から先祖の生活文化を推論するのと同じ文脈だ。きちんとした記録を残さないと、1000年後の考古学者らはゴミ捨て場に捨てられたラーメンの袋を見て「先祖の主食ラーメンだった」と考えながら我々の生活方式を推論しかねない。
- 安東(アンドン)という典型的な儒教文化圏の出身だが、大家族ならではの特別な「情」というものがありそうだ。今日の自分の原点となった、幼い頃、大家族の中で経験した特別なものがあるとしたら。
一言で言うと「自由」だ。名門校に通ったわけでもなく、いわゆる「両班(ヤンバン)」の家柄で育ったわけでもないが、今日の自分があるのは「安東」という文化的背景で成長したからだと思う。安東で育った分、他の地域の同年代とは伝統文化に対する視点が少し違っていたかも知れない。私の文化的なベースが安東であるという点は誇りでもある。今日の自分はそのベースに加え、民俗学を勉強したという看板があってのものだと思う。
民俗学は現場の学問だ。現場に行ってお年寄りの話を聞くことで知識を得ることができる。大人と自然に接する方法を身に付けられたバックグランドが、ここで役に立った。名門大学や人気の学科など学閥や看板がものを言う時代だが、そうでない者として誰かにモチベーションを与えることができるなら、それだけでも自分の役割は果たしていると思う。

- 今日の韓国社会は儒教文化からかなり遠ざかっているように思える。儒教文化を否定的に捉える見方もある。そんな中でも、我々が受け継ぎ、世界と共有すべき儒教的価値とは。
我々は過度に儒教を批判し、貶めてるように思う。昔は、ある村で誰かが飢えで死ぬようものなら、その村は人の住むような地ではないとされた。これは、儒教の利他的な考え方によるものだ。儒教は世界的なリーダーを育てるものにもなり得る。これは、ソンビ文化修練院(ソンビ:学識が高く高尚な人)のキム・ビョンイル院長の著書『ソンビのように、退渓(テゲ)のように』からもよくわかる。この本では、儒教のソンビ精神の例として世界銀行のジム・ヨン・キム総裁を挙げている。キム総裁はもともと医者で、人類学を専攻した。彼の母親は朝鮮の儒学者である退渓李滉(イ・ファン)を研究した学者だった。当初、医術を以って人類のために貢献しようと考えたキム総裁は、やがて大学の学長を経て、今では世界銀行総裁という立場で人類への貢献を実践している。儒教における人類に対する奉仕と博愛、利他的な生活、尊敬、自分には厳しく他人には寛大な「慎独」は我々が共有すべき価値だ。
職業としての学問ではなく、人生としての人文学を勉強すべきだ。数年前の「宗家特別展」を行う際に、周りから尊敬されながら数百年も続いてきた宗家の秘訣について研究したことがある。「腹を空かせた者は誰でも米びつから米を取り出しても構わない」という意味の「他人能解」を実践し、大きな壷に米を入れて人々と分かち合った求禮(クレ)の文化柳(ムンファ・リュ)氏、安東金(アンドン・キム)氏、慶州崔(キョンジュ・チェ)氏など周りから尊敬された宗家には、自分だけでなく周囲を顧みながら共存を図ったという共通点がある。
人文学は金にはならないが、人生における重要な役割を持っている。かつて、共に生きるための米びつがなかったら、どの宗家も周りから嫌われ滅びたはずだ。しかし実際には、宗家が歴史的・政治的危機に直面するたびに、むしろ周りの人々が進んで宗家を守ったのだ。宗家が代々続いて来れたのは、人間を思いやる人本的な価値を実践したからであり、謙遜と配慮、共に生きるという家訓のおかげだった。生きる方法、人間らしく生きる方向性という側面から人文学へアプローチし、生きるうえでの癒しを求めるべきだ。今日の人文学講義のように、頭だけで人文学を理解しようとしてはならない。
頭で学ぶ知識と、心で学び肌で体験する知識には違いがある。学校で学ぶのは、頭で学ぶ知識だ。一方で、博物館の教育は遺物を見ながら直接作ったり体験するなど体で学ぶものだ。博物館の教育は現場にあり、体験を基に多様な方法で行われるので、学校の教育とは異なるメリットがある。このようなメリットを活かして様々な方法を通じて心で学び、肌で体験し、長く記憶に残る形で教育を企画できればと思う。
教育の対象も過去には青少年や専門家向けがほとんどで、お年寄りのための教育は十分でなかった。国立民俗博物館では、健康に生きるための漢方や健康食などお年寄り向けの教育と、高齢者文化をテーマとした高齢者特別展などを企画中だ。これらを通じて、より幅広い年齢層・階層の方々が交流できればと思う。お年寄りの考え方と知恵を学べる展示になるものと期待している。
- 今後、企画してみたいテーマや展示はあるか。
ジャンク展と砂糖をテーマにした展示、香りに関する展示をやってみたい。とくに、砂糖は人類の文明史において重要な意味がある。
ジャンク展のアイディアは、昨年の国際セミナーでジャンク展のアイディアを発表したフランス国立民俗美術館のキュレーターにインスパイアされたものだ。その発表者に、フランスでは地中海を中心としたジャンク展、韓国では韓国を中心としたジャンク展を同時に行うのはどうかと提案した。現在、関連の学術セミナーなどを推進中で、展示は2017年の夏かそれ以降になる予定だ。昔はどれももったいなくて、物をよく捨てなかった。着古した服を縫い合わせて風呂敷を作ったり、ほうきの1本もむやみに捨てなかった。それに比べて今はどうだろうか。ジャンクアート、ゴミをあさって生きる人、個人が捨てるゴミの量、リサイクル、環境と地球の将来など様々な展示を扱うことができる。
香りに関する展示についてだが、例えばシャネルのNo.5など有名ブランドは香水でトータルファッションを完成させる。なのに韓国では香りと言っても思い浮かべるのは、せいぜい祭事で焚くお香ぐらいだ。これには日頃から疑問を抱いている。
- 突飛な質問かも知れないが、人々が博物館に訪れるべき理由は何だと考えるか。
博物館にはただ気軽に遊びに来てもらいたい。何か特別な経験をしに行くなどの期待はなくたっていい。行きたいと思ったときに来ればいい。博物館に来る人は大きく3つに分けられる。勉強しに来る人、食べに来る人、遊びに来る人だ。大多数の観覧客は勉強をしに博物館に来るが、単に知識を得るためだけに博物館に訪れるのは面白みがないのでは。博物館に食べたり、遊びに来る方々のために、全国の有名菓子店の人気メニューなどを博物館で味わえるようにして「おいしい博物館」を作ることができれば、きっとよりたくさんの人々が博物館に足を運ぶはずだ。
国立民俗博物館は2014年基準で、オフライン350万人(約65%が外国人)・オンライン250万人の観覧客が訪れた。「訪問型博物館」事業を通じて年間30万人の人が博物館に訪れたのだ。これからも様々な方法で、より多くの人々にアプローチするために研究を続ける計画だ。
- 博物館を「鏡」に例えたが、「歴史という名の鏡」「自分を映し出す鏡」という意味だろうか。博物館という鏡を通して我々がすべきこととは何か。
過去の過ちを繰り返すことがあってはならない。鏡で前、横、後ろからの姿が見られるように、博物館ではいろんな角度から過去を見ることができる。鏡を通して自分の姿を見るように、博物館を通して自分の知らなかった過去や未来を見ることができるのだ。
博物館は遺物を基に伝統文化を展示する。ただ、そこから過去だけではなく、現在や未来の人類ついても語らなければならない。歴史と文化は過去を振り向くためよりも、未来を見通すためのものなのだ。
コリアネット ユン・ソジョン記者
写真:コリアネット チョン・ハン記者
arete@korea.kr





これらはどれも国立民俗博物館が所蔵する遺物で、ホームページで一目で検索できる資料だ。
国立民俗博物館は昨年11月、所蔵遺物の99%にあたる68,000点余りの飼料をすべて一般に公開した。最近では、グーグルの美術プログラム(Fine Arts Program)から資料活用協力(MOU)の提案もあった。所蔵品の大々的な公開は、世界的にも国立民俗博物館が初めてだからだ。ここには、千鎮基(チョン・ジンギ)館長の信念が込められている。
チョン館長の信念は博物館の情報化だけでなく、博物館の展示や役割に対する考えからも窺える。コリアネットは、チョン館長に博物館の進むべき道と民俗・文化・歴史についての考えを尋ねた。
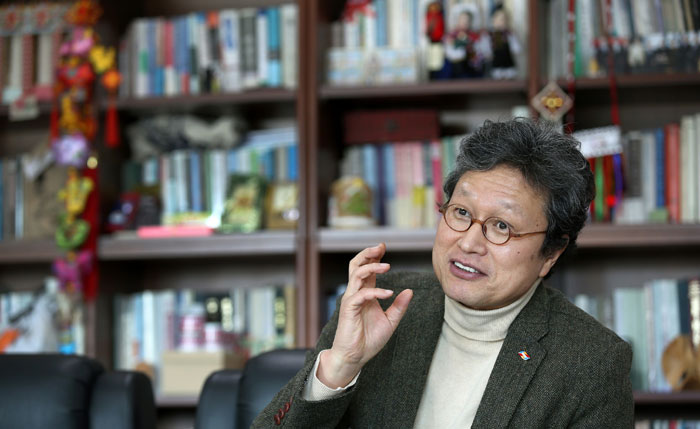
国立民俗博物館の千鎮基館長は「博物館は誰もが気楽に来れる居心地の良い場所でなければならない」と強調する
- 日常生活から国家間の交流にいたるまで展示の幅が広くなった。従来の「民俗」という概念を超えているように思えるが、どのような背景があるのか。
現在展示中の「飯膳の交わり」や「ジーンズ」などに次いで、再来年には「ジャンク(junk、ゴミ)」展も行う予定だ。この展示が成立し得るのは「民俗」の幅が広いからだ。また、国立民俗博物館は3年に一度は現代の世に強いメッセージを投げかけるべきだと考えている。
「ジーンズ」展は、英国のある人類学者のジーンズに関する報告書からアイディアを得た。その後、リーバイスの博物館に訪れたり、国内のアパレルメーカー「BANG BANG」などの歴史を顧たりと3年間に渡って調査をした。ジーンズをセクシーだと考える米国の80代の寄贈者の考え方とライフスタイル、1本500万円を上回る日本のプレミアムジーンズなど、皆が共感を抱ける「ジーンズ」という共通のアイテムであっても互いに異なる視点があるということがわかった。一方で、「飯膳の交わり」では空間・映像・音響など様々な分野におけるキュレーターやプロデューサーらの参加の下アイデアを構成し、360度回転可能な映像など新しい試みにも挑んだ。

韓日両国の食文化を紹介した「飯膳の交わり」は、実際に料理を食べながら体験できる。展示は2月29日まで。写真は、7日に観覧客が「飯膳の交わり」展を観覧している様子
- 文化生産者は増える反面、消費者は伸び悩んでいるようだ。原因と対策を伺いたい。
多くの人々が博物館の利用方法を知らないがために、単に勉強だけが目的となっている。このように文化生産者によって生産される文化の総量に比べて、文化の利用方法に対する消費者の知識が足りないのが原因ではないだろうか。文化生産者には、生産する前にできるだけ消費者の立場で考える配慮が求められる。
「猿のお尻は赤い」展を例に挙げるなら、母猿が小猿を抱いている青磁母子猿形硯滴を単に「青磁、猿の親子、硯滴」と捉えるのではなく、この遺物を見ながら涙することができなくてはならない。幼い子供を亡くした方、両親を亡くした方はこの遺物をみて涙しながら慰めを得られる思う。作品に家族愛と母性愛が込められているからだ。涙を流し慰めを得ることで心にゆとりができると、今度は猿や青磁の色にも目が行くようになる。そうすれば、その遺物を目ではなく心で感じることができる。こうなるためには博物館が心地よい場所でなければならない。単に知識を得るために博物館に訪れるのではなく、食べるために、遊ぶために来てもらえるようにしなくてはならないのだ。博物館を通して、人々の歴史と文化を見る観点と博物館に対する認識が変わることを期待したい。
- 国立民俗博物館は2010年からベトナム、モンゴル、フィリピン、ウズベキスタン、韓国、中国の文化を紹介する「多文化の箱」事業を運営中だ。異文化研究事業を続けるうえで追求している点はあるか。
文化は両方向からの疎通が必要だ。韓国の文化を発信するだけでなく、他の文化についても視野を広げ、人類が如何に共に調和をなして共存共栄するかを考えなくてはならない。そこで文化的なアプローチが一つの方法になり得るのではないだろうか。その延長線上で祖国と民族、人類の共存のために国立民俗博物館ができることの一つが「多文化の箱」事業なのだと思う。もとより、この事業の趣旨は異文化を共有し理解を広めることだった。
まずは、多文化に対する認識を変える必要がある。韓国の観点からのみ考えるのではなく、相手の立場になって考えなければならない。ベトナム人の嫁に韓国の文化を強要するのではなく、ベトナムの文化・言語などを少しずつ理解し分かち合えば、家族全員が幸せになれると思う。
韓・日・中3国はいずれも箸を使うが、形も素材もまちまちだ。各々の食文化があるからだ。この違いを変に捉えるのではなく、互いに理解しなければならない。文化に対する理解を通して人類愛を育むために、このような事業や比較展示を行ってきた。

チョン館長は自国の文化を一方的に発信するのではなく、異文化に対する理解を広めることで人類共存と共栄に貢献できると語る。各国の民俗工芸品を紹介するチョン館長
我々は大量生産・消費の時代を生きている。例えば、大型スーパーで取り扱う品数は3~4万種類にも上るそうだが、この中から何かを買うとする。しかし、それを媒介に共有する空間・ヒト・モノが融合しなければ何の意味も成せないのである。現代の遺物を収集するうえで、博物館では家庭における所帯道具が全部で何個かを一つひとつチェックする。この調査を経て「所帯道具」のカタログを年に3回作っている。遺物カードのように数や種類、位置情報などをすべて調査して写真を撮って記録する形だ。この過程で寄贈を募集することもある。そうすると後々その家をそのまま再現することもできる。このように文化的な状況の中に入り込んだ遺物、つまり使った人・時期・場所のデータがあるもは所蔵価値があると判断できる。今すぐはそうでなくても、10年後には意味のあるものとなるのだ。
「今」をどのように記録して収集するのか、また将来どうやって再現するのかについて考えなければならない。これは、我々が貝塚から先祖の生活文化を推論するのと同じ文脈だ。きちんとした記録を残さないと、1000年後の考古学者らはゴミ捨て場に捨てられたラーメンの袋を見て「先祖の主食ラーメンだった」と考えながら我々の生活方式を推論しかねない。
- 安東(アンドン)という典型的な儒教文化圏の出身だが、大家族ならではの特別な「情」というものがありそうだ。今日の自分の原点となった、幼い頃、大家族の中で経験した特別なものがあるとしたら。
一言で言うと「自由」だ。名門校に通ったわけでもなく、いわゆる「両班(ヤンバン)」の家柄で育ったわけでもないが、今日の自分があるのは「安東」という文化的背景で成長したからだと思う。安東で育った分、他の地域の同年代とは伝統文化に対する視点が少し違っていたかも知れない。私の文化的なベースが安東であるという点は誇りでもある。今日の自分はそのベースに加え、民俗学を勉強したという看板があってのものだと思う。
民俗学は現場の学問だ。現場に行ってお年寄りの話を聞くことで知識を得ることができる。大人と自然に接する方法を身に付けられたバックグランドが、ここで役に立った。名門大学や人気の学科など学閥や看板がものを言う時代だが、そうでない者として誰かにモチベーションを与えることができるなら、それだけでも自分の役割は果たしていると思う。

チョン館長は、他人に対する配慮や謙遜など儒教的な価値は今を生きる皆が共有すべきものだと強調する
- 今日の韓国社会は儒教文化からかなり遠ざかっているように思える。儒教文化を否定的に捉える見方もある。そんな中でも、我々が受け継ぎ、世界と共有すべき儒教的価値とは。
我々は過度に儒教を批判し、貶めてるように思う。昔は、ある村で誰かが飢えで死ぬようものなら、その村は人の住むような地ではないとされた。これは、儒教の利他的な考え方によるものだ。儒教は世界的なリーダーを育てるものにもなり得る。これは、ソンビ文化修練院(ソンビ:学識が高く高尚な人)のキム・ビョンイル院長の著書『ソンビのように、退渓(テゲ)のように』からもよくわかる。この本では、儒教のソンビ精神の例として世界銀行のジム・ヨン・キム総裁を挙げている。キム総裁はもともと医者で、人類学を専攻した。彼の母親は朝鮮の儒学者である退渓李滉(イ・ファン)を研究した学者だった。当初、医術を以って人類のために貢献しようと考えたキム総裁は、やがて大学の学長を経て、今では世界銀行総裁という立場で人類への貢献を実践している。儒教における人類に対する奉仕と博愛、利他的な生活、尊敬、自分には厳しく他人には寛大な「慎独」は我々が共有すべき価値だ。
職業としての学問ではなく、人生としての人文学を勉強すべきだ。数年前の「宗家特別展」を行う際に、周りから尊敬されながら数百年も続いてきた宗家の秘訣について研究したことがある。「腹を空かせた者は誰でも米びつから米を取り出しても構わない」という意味の「他人能解」を実践し、大きな壷に米を入れて人々と分かち合った求禮(クレ)の文化柳(ムンファ・リュ)氏、安東金(アンドン・キム)氏、慶州崔(キョンジュ・チェ)氏など周りから尊敬された宗家には、自分だけでなく周囲を顧みながら共存を図ったという共通点がある。
人文学は金にはならないが、人生における重要な役割を持っている。かつて、共に生きるための米びつがなかったら、どの宗家も周りから嫌われ滅びたはずだ。しかし実際には、宗家が歴史的・政治的危機に直面するたびに、むしろ周りの人々が進んで宗家を守ったのだ。宗家が代々続いて来れたのは、人間を思いやる人本的な価値を実践したからであり、謙遜と配慮、共に生きるという家訓のおかげだった。生きる方法、人間らしく生きる方向性という側面から人文学へアプローチし、生きるうえでの癒しを求めるべきだ。今日の人文学講義のように、頭だけで人文学を理解しようとしてはならない。
頭で学ぶ知識と、心で学び肌で体験する知識には違いがある。学校で学ぶのは、頭で学ぶ知識だ。一方で、博物館の教育は遺物を見ながら直接作ったり体験するなど体で学ぶものだ。博物館の教育は現場にあり、体験を基に多様な方法で行われるので、学校の教育とは異なるメリットがある。このようなメリットを活かして様々な方法を通じて心で学び、肌で体験し、長く記憶に残る形で教育を企画できればと思う。
教育の対象も過去には青少年や専門家向けがほとんどで、お年寄りのための教育は十分でなかった。国立民俗博物館では、健康に生きるための漢方や健康食などお年寄り向けの教育と、高齢者文化をテーマとした高齢者特別展などを企画中だ。これらを通じて、より幅広い年齢層・階層の方々が交流できればと思う。お年寄りの考え方と知恵を学べる展示になるものと期待している。
- 今後、企画してみたいテーマや展示はあるか。
ジャンク展と砂糖をテーマにした展示、香りに関する展示をやってみたい。とくに、砂糖は人類の文明史において重要な意味がある。
ジャンク展のアイディアは、昨年の国際セミナーでジャンク展のアイディアを発表したフランス国立民俗美術館のキュレーターにインスパイアされたものだ。その発表者に、フランスでは地中海を中心としたジャンク展、韓国では韓国を中心としたジャンク展を同時に行うのはどうかと提案した。現在、関連の学術セミナーなどを推進中で、展示は2017年の夏かそれ以降になる予定だ。昔はどれももったいなくて、物をよく捨てなかった。着古した服を縫い合わせて風呂敷を作ったり、ほうきの1本もむやみに捨てなかった。それに比べて今はどうだろうか。ジャンクアート、ゴミをあさって生きる人、個人が捨てるゴミの量、リサイクル、環境と地球の将来など様々な展示を扱うことができる。
香りに関する展示についてだが、例えばシャネルのNo.5など有名ブランドは香水でトータルファッションを完成させる。なのに韓国では香りと言っても思い浮かべるのは、せいぜい祭事で焚くお香ぐらいだ。これには日頃から疑問を抱いている。
- 突飛な質問かも知れないが、人々が博物館に訪れるべき理由は何だと考えるか。
博物館にはただ気軽に遊びに来てもらいたい。何か特別な経験をしに行くなどの期待はなくたっていい。行きたいと思ったときに来ればいい。博物館に来る人は大きく3つに分けられる。勉強しに来る人、食べに来る人、遊びに来る人だ。大多数の観覧客は勉強をしに博物館に来るが、単に知識を得るためだけに博物館に訪れるのは面白みがないのでは。博物館に食べたり、遊びに来る方々のために、全国の有名菓子店の人気メニューなどを博物館で味わえるようにして「おいしい博物館」を作ることができれば、きっとよりたくさんの人々が博物館に足を運ぶはずだ。
国立民俗博物館は2014年基準で、オフライン350万人(約65%が外国人)・オンライン250万人の観覧客が訪れた。「訪問型博物館」事業を通じて年間30万人の人が博物館に訪れたのだ。これからも様々な方法で、より多くの人々にアプローチするために研究を続ける計画だ。
- 博物館を「鏡」に例えたが、「歴史という名の鏡」「自分を映し出す鏡」という意味だろうか。博物館という鏡を通して我々がすべきこととは何か。
過去の過ちを繰り返すことがあってはならない。鏡で前、横、後ろからの姿が見られるように、博物館ではいろんな角度から過去を見ることができる。鏡を通して自分の姿を見るように、博物館を通して自分の知らなかった過去や未来を見ることができるのだ。
博物館は遺物を基に伝統文化を展示する。ただ、そこから過去だけではなく、現在や未来の人類ついても語らなければならない。歴史と文化は過去を振り向くためよりも、未来を見通すためのものなのだ。
コリアネット ユン・ソジョン記者
写真:コリアネット チョン・ハン記者
arete@korea.kr

国立民俗博物館の全景

旧正月前日の7日、国立民俗博物館を訪れた観覧客が博物館の広場で韓国の伝統遊戯ユンノリをしている

国立民俗博物館広場でのプンムルノリ公演

国立民俗博物館の前には、独立後のソウルを走っていた電車と当時の村の様子が再現されてある

観覧客を迎える国立民俗博物館のチャンスンとソッテ
