45歳の小説家が生と死、愛と渇望について語る。それは非常に典型的な構成だ。
「誰かがそう言っていました。永遠の国があるって。我らは皆この世にしばし留まるためにそこから訪れた鳥だと。後でそちらに行ったらどうか生を繰り返さずに長らく留まってください。あの永遠の国に」(『ツバメを飼う』本文より)
韓国政府の公式文学広報機関の韓国文学翻訳院がこれまで出版した韓国小説の英語版は幅広い韓国文学のごく一部だけを紹介している。韓国文学翻訳院から発刊された作品は1950年代、または 経済成長期の1980年代を背景にした短編または中編小説が典型的で、複数の文学賞を受賞した中年男性作家の作品が主流となっている。
金承鈺(キム・スンオク)の『霧津紀行』(1964)と『ソウル1964年冬』(1965)もそれに当たる。中でも上記2作は最高といえるだろう。金周栄(キム・ジュヨン)の中篇小説『ガンギレイ』(1998)もそうであり、蔣正一(チャン・ジョンイル)の『アダムが目を覚ますとき』(1990)はそれまでの典型的な構成に放蕩さを少しプラスした作品。玄基栄(ヒョン・ギヨン)の『地上に匙ひとつ』(1999)は大虐殺と政治、実際の歴史話が加わっている。金源一(キム・ウォニル)の『庭の深い家』(1998)、崔仁勳(チェ・インフン)の『広場』(1960)も同じカテゴリーに分類される。これらのうち2、3作を読んでみるとそれがわかるはずだ。
韓国文学翻訳院が出版した作品だけで韓国文学を評価するなら、韓国の文学作品は似たり寄ったりの中年男性作家が同じような話を繰り返しているということになるかもしれない。 違いといえば不自然な英語の文章と翻訳、明確さに欠けた形式と間違ったスペルくらいだろうか。
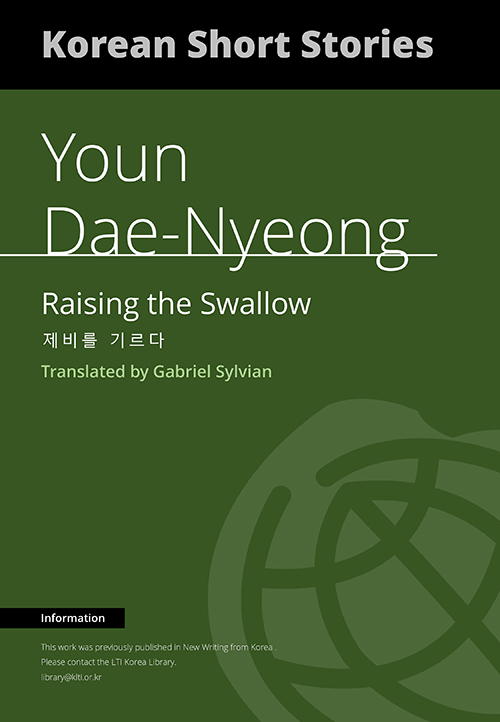
にもかかわらず、韓国文学翻訳院が尹大寧作家の『ツバメを飼う』を英語翻訳していなければおそらく私がこの作品を読むことはなかっただろう。この作品には感動がある。少年が一人の男性に成長していく過程を受け入れる、ある意味一種の見本のようなものだ。主人公は空想にふけがちで感性的な上、誤解に起因する怒りと涙を抱えている。ヒロインは乾いた心の典型的な人物。同作は男性の立場から書いた男性の物語である。
 作家の尹大寧は、平凡な家庭に生まれ少しおかしく見えるキャラクターの母親のもとで育ったある男性の成長ストーリーを描いている。たぶん作家自身の話であろう。作中の母親は毎年冬になると2週間も姿をくらます。ツバメが巣に帰らなくなった日からのことだった。男の幼年期は巣から落ちた小鳥の世話をする記憶から始まる。20代後半になった男は少年時代を過ごしたソウル外れの家を再び訪れ、昔のツバメたちが依然としてそこに住んでいるのを目にする。ツバメは一生彼の周辺を飛び回る。そして我々は皆人生という旅路を進むツバメだ。
作家の尹大寧は、平凡な家庭に生まれ少しおかしく見えるキャラクターの母親のもとで育ったある男性の成長ストーリーを描いている。たぶん作家自身の話であろう。作中の母親は毎年冬になると2週間も姿をくらます。ツバメが巣に帰らなくなった日からのことだった。男の幼年期は巣から落ちた小鳥の世話をする記憶から始まる。20代後半になった男は少年時代を過ごしたソウル外れの家を再び訪れ、昔のツバメたちが依然としてそこに住んでいるのを目にする。ツバメは一生彼の周辺を飛び回る。そして我々は皆人生という旅路を進むツバメだ。
『ツバメを飼う』(2007)は1970年代と1980年代に成長期を過ごした男の物語だ。シンプルな構成で編み上げられた同作の内容は韓国の男性なら誰もが共感できるものになっている。この類の小説がそうであるように、主人公はそのカテゴリーに属する作家が描く一般的な経験をしながら生きていく。前述したようにこの作品も典型に基づいて書かれている。小さい頃には絶えず虐待を受け、家庭内不和と間違った子育て、親から十分な愛情をもらえてない子供がいる。
泥だらけの農地からいきなり多くのガラスと鉄が出てくる。韓国の経済成長を意味するものだろうか。そうだ。軍隊経験の話も登場する。軍隊は韓国の男性同士の連帯を意味するものなのか。そうだ。初めて女性に接したときの不器用さもある。女性と対等に向き合えない韓国男性の話なのか。そうだ。
フランスのヌーヴェル・ヴァーグ(Nouvelle Vague、1950年代半ばから始まったフランスにおける映画の革新運動)映画のように、この作品は過度に劇化されているのに何の出来事も起こらない場面が長く続いたりする。昔の田舎風景と暴力を振るう父から自分を守ってくれた暖かい母親もいる。
同作は韓国の男性について語っている。この作品が幅広い読者から共感を得られるとは思えない。私はページをめくりながら最後まで小説を楽しんだのだが、それはやはり私も韓国に暮らす41歳の外国人男性だということなのだろう。
「ちょうどその時間に私は数百、いや数千のツバメの群れが野原のあちこちを覆っている場面を見つめていた。ある群れは空を低く飛びながらジージー、チュピチュピと群がったり、他は摩尼山(マニサン)の方に一気に飛んでいってはまたバス停の前へと飛んでくることもあった」 (本文より)
作品には作家の心理を垣間見れる場面もある。
「皆が戻ってくるわけではないみたいですね」
「…しかも子鳥が戻ってくる確立は1%に過ぎないそうだよ」
「じゃあ、残りのツバメは皆どこに行ってしまうのでしょう」
「一部は命が尽きて死ぬし、残りのツバメは別の場所に行くのだろう」
一部は命が尽きて死ぬし、残りは別の場所へ行く。この場面と最後のシーンは作家が考える人生を例えたものだといえる。一部は命が尽きて死ぬ。そして残りは別の場所へと行く。悟りも楽しさもない。ただちょっとだけ感動的だ。
あらすじを見ると、感性豊かな大学生が兵役に服している時期にある女性に出会う。彼らはデートをしてタイを一緒に旅する。彼女には別の恋人がいる。彼らはタイでツバメの群れを見かける。男の母が彼女に会ったときもツバメの話をする。男は苦しい人生を送りながら漂流する。居酒屋の屋根にツバメの群れが集まる。2000年代半ば、それぞれ配偶者と子供がいるがあまり幸せでない2人が再開したときも、ツバメの群れが現れる。
「いつか石が転がる音が止まったら、そのとき帰ります。それまではここを離れません」 (本文より)
女はある瞬間カタルシスを得る。田舎の高速道路、深夜、嵐の中で彼女はある老人からデウス・エクス・マキナ(古代ギリシャ劇の終幕で上方から機械仕掛けで舞台に降り、紛糾した事態を円満に収拾する神の役割)のような拠り所を探しまわる。彼女の魂は粉々に打ち砕かれる。彼女こそパ・ドゥ・ドゥ(バレエ作品において男女2人の踊り手によって展開される踊り)の唯一の、本物の演者である。男性はストーリーが終わるまで何もしない。彼にはキャラクターがない。しかし女性は自分の人生を切り開いていく。
「それとともに急流の中から岩々がガラガラと押し流される音が聞こえてきた。夜の間夢の中で聞いていたその音だった。岩が水の中で転がる音を聞きながらムニはついに号泣してしまった。まるで自分の魂が崩れ落ちるような音に聞こえたのだ」 (本文より)
尹大寧作家がこの作品で一番集中したのは幼年期を振り返るある中年男性の姿を表現することだった。ツバメの群れが空を飛ぶ。ツバメは彼を江華島(カンファド)からソウルへ、ソウルからまた江華島へと導く。
『ツバメを飼う』の英語版は作家の声をそのまま映している。人間の歴史を、いや自分自身の人生を見つめる作家の視線を上手く捕らえた。
自分の子供が生まれると、彼はもう一羽の「ツバメ」を飼う。
「驚くことに子供は成長しながら後ろ髪にツバメの尾のようなクセができた。実は幼い頃の私にもそんなクセ毛があったのだ」(本文より)
コリアネット グレゴリー・イーヴス記者
写真:韓国文学翻訳院
翻訳:コリアネット ソン・ジエ記者、イム・ユジン
gceaves@korea.kr
韓国政府の公式文学広報機関の韓国文学翻訳院がこれまで出版した韓国小説の英語版は幅広い韓国文学のごく一部だけを紹介している。韓国文学翻訳院から発刊された作品は1950年代、または 経済成長期の1980年代を背景にした短編または中編小説が典型的で、複数の文学賞を受賞した中年男性作家の作品が主流となっている。
金承鈺(キム・スンオク)の『霧津紀行』(1964)と『ソウル1964年冬』(1965)もそれに当たる。中でも上記2作は最高といえるだろう。金周栄(キム・ジュヨン)の中篇小説『ガンギレイ』(1998)もそうであり、蔣正一(チャン・ジョンイル)の『アダムが目を覚ますとき』(1990)はそれまでの典型的な構成に放蕩さを少しプラスした作品。玄基栄(ヒョン・ギヨン)の『地上に匙ひとつ』(1999)は大虐殺と政治、実際の歴史話が加わっている。金源一(キム・ウォニル)の『庭の深い家』(1998)、崔仁勳(チェ・インフン)の『広場』(1960)も同じカテゴリーに分類される。これらのうち2、3作を読んでみるとそれがわかるはずだ。
韓国文学翻訳院が出版した作品だけで韓国文学を評価するなら、韓国の文学作品は似たり寄ったりの中年男性作家が同じような話を繰り返しているということになるかもしれない。 違いといえば不自然な英語の文章と翻訳、明確さに欠けた形式と間違ったスペルくらいだろうか。
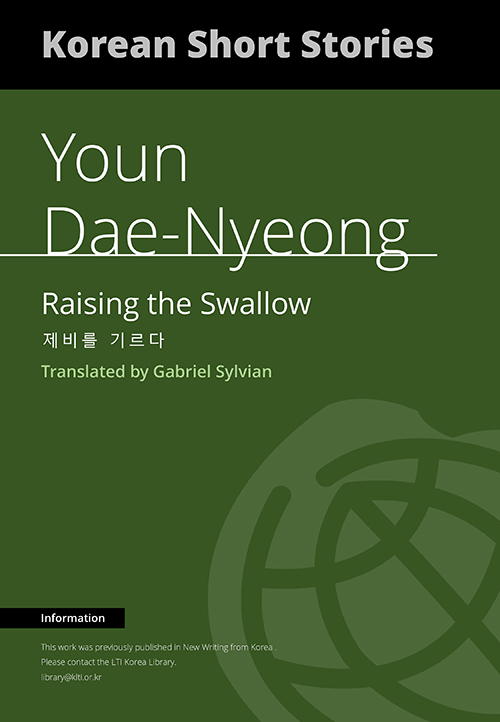
尹大寧作家は2007年に短編小説『ツバメを飼う』を発表した。2008年に英語版が出た同作の翻訳はガブリエル・シルヴィアンが担当した
にもかかわらず、韓国文学翻訳院が尹大寧作家の『ツバメを飼う』を英語翻訳していなければおそらく私がこの作品を読むことはなかっただろう。この作品には感動がある。少年が一人の男性に成長していく過程を受け入れる、ある意味一種の見本のようなものだ。主人公は空想にふけがちで感性的な上、誤解に起因する怒りと涙を抱えている。ヒロインは乾いた心の典型的な人物。同作は男性の立場から書いた男性の物語である。

1962年生まれの尹大寧作家は水が流れるかのように滑らかで叙情的な文章で有名な韓国を代表する小説家
『ツバメを飼う』(2007)は1970年代と1980年代に成長期を過ごした男の物語だ。シンプルな構成で編み上げられた同作の内容は韓国の男性なら誰もが共感できるものになっている。この類の小説がそうであるように、主人公はそのカテゴリーに属する作家が描く一般的な経験をしながら生きていく。前述したようにこの作品も典型に基づいて書かれている。小さい頃には絶えず虐待を受け、家庭内不和と間違った子育て、親から十分な愛情をもらえてない子供がいる。
泥だらけの農地からいきなり多くのガラスと鉄が出てくる。韓国の経済成長を意味するものだろうか。そうだ。軍隊経験の話も登場する。軍隊は韓国の男性同士の連帯を意味するものなのか。そうだ。初めて女性に接したときの不器用さもある。女性と対等に向き合えない韓国男性の話なのか。そうだ。
フランスのヌーヴェル・ヴァーグ(Nouvelle Vague、1950年代半ばから始まったフランスにおける映画の革新運動)映画のように、この作品は過度に劇化されているのに何の出来事も起こらない場面が長く続いたりする。昔の田舎風景と暴力を振るう父から自分を守ってくれた暖かい母親もいる。
同作は韓国の男性について語っている。この作品が幅広い読者から共感を得られるとは思えない。私はページをめくりながら最後まで小説を楽しんだのだが、それはやはり私も韓国に暮らす41歳の外国人男性だということなのだろう。
「ちょうどその時間に私は数百、いや数千のツバメの群れが野原のあちこちを覆っている場面を見つめていた。ある群れは空を低く飛びながらジージー、チュピチュピと群がったり、他は摩尼山(マニサン)の方に一気に飛んでいってはまたバス停の前へと飛んでくることもあった」 (本文より)
作品には作家の心理を垣間見れる場面もある。
「皆が戻ってくるわけではないみたいですね」
「…しかも子鳥が戻ってくる確立は1%に過ぎないそうだよ」
「じゃあ、残りのツバメは皆どこに行ってしまうのでしょう」
「一部は命が尽きて死ぬし、残りのツバメは別の場所に行くのだろう」
一部は命が尽きて死ぬし、残りは別の場所へ行く。この場面と最後のシーンは作家が考える人生を例えたものだといえる。一部は命が尽きて死ぬ。そして残りは別の場所へと行く。悟りも楽しさもない。ただちょっとだけ感動的だ。
あらすじを見ると、感性豊かな大学生が兵役に服している時期にある女性に出会う。彼らはデートをしてタイを一緒に旅する。彼女には別の恋人がいる。彼らはタイでツバメの群れを見かける。男の母が彼女に会ったときもツバメの話をする。男は苦しい人生を送りながら漂流する。居酒屋の屋根にツバメの群れが集まる。2000年代半ば、それぞれ配偶者と子供がいるがあまり幸せでない2人が再開したときも、ツバメの群れが現れる。
「いつか石が転がる音が止まったら、そのとき帰ります。それまではここを離れません」 (本文より)
女はある瞬間カタルシスを得る。田舎の高速道路、深夜、嵐の中で彼女はある老人からデウス・エクス・マキナ(古代ギリシャ劇の終幕で上方から機械仕掛けで舞台に降り、紛糾した事態を円満に収拾する神の役割)のような拠り所を探しまわる。彼女の魂は粉々に打ち砕かれる。彼女こそパ・ドゥ・ドゥ(バレエ作品において男女2人の踊り手によって展開される踊り)の唯一の、本物の演者である。男性はストーリーが終わるまで何もしない。彼にはキャラクターがない。しかし女性は自分の人生を切り開いていく。
「それとともに急流の中から岩々がガラガラと押し流される音が聞こえてきた。夜の間夢の中で聞いていたその音だった。岩が水の中で転がる音を聞きながらムニはついに号泣してしまった。まるで自分の魂が崩れ落ちるような音に聞こえたのだ」 (本文より)
尹大寧作家がこの作品で一番集中したのは幼年期を振り返るある中年男性の姿を表現することだった。ツバメの群れが空を飛ぶ。ツバメは彼を江華島(カンファド)からソウルへ、ソウルからまた江華島へと導く。
『ツバメを飼う』の英語版は作家の声をそのまま映している。人間の歴史を、いや自分自身の人生を見つめる作家の視線を上手く捕らえた。
自分の子供が生まれると、彼はもう一羽の「ツバメ」を飼う。
「驚くことに子供は成長しながら後ろ髪にツバメの尾のようなクセができた。実は幼い頃の私にもそんなクセ毛があったのだ」(本文より)
コリアネット グレゴリー・イーヴス記者
写真:韓国文学翻訳院
翻訳:コリアネット ソン・ジエ記者、イム・ユジン
gceaves@korea.kr
